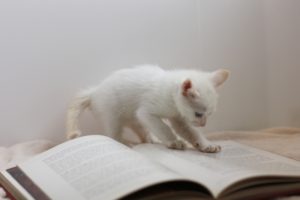SNSで「猫の無償譲渡」をうたった詐欺が相次いでいます。この記事では、報道で取り上げられた事例を紹介するとともに、獣医師としての見解を交え、注意点をわかりやすくお伝えします。
報道概要:SNSの「無償譲渡」でエサ代・保険料を請求
2024年4月29日、Yahoo!ニュースが報じたフジテレビ「イット!」の独自取材によると、SNS上で「子猫を無償で譲渡する」とうたって金銭を騙し取るトラブルが相次いでいる。
報道によれば、ある「X」と名乗る人物がSNSで「猫舎閉鎖に伴う無償譲渡」を装い、接触してきた希望者に対してエサ代・保険料などの名目で約3万円の支払いを求めた上、猫の受け取り先として無関係な保護団体やブリーダーの住所を無断で使用していたという。
実際に大阪府の保護団体「ねこから目線。」には、事前連絡もなく猫の引き取りに訪れる人が現れ、団体の代表は「詐欺に利用されて非常に迷惑している」と憤りを隠さない。
また、東京都内でも同様の事例があり、無関係の犬のブリーダー宅に猫の引き渡しを求める人が押しかけるなど、複数の場所で「X氏」の手口とみられる被害が確認されている。
専門家である弁護士は、「これは明らかに詐欺の手口と考えられ、保険料が後から返金されるという説明も通常の保険制度にはない」と指摘している。
獣医師としての見解:「善意」の譲渡文化が搾取に利用される危うさ
獣医師として、長年動物福祉と向き合ってきた立場から見ても、このような詐欺行為には強い憤りを感じます。
ここ十数年、日本における犬猫の殺処分数は着実に減少しており、環境省によると、令和4年度の殺処分数は犬が2,810頭、猫が15,650頭と、ピーク時に比べ大幅な改善がみられます。この背景には、全国の保護団体や個人ボランティアによる献身的な活動があることは言うまでもありません。
しかし一方で、SNSやクラウドファンディングを活用して「保護活動」をうたう個人・団体の中には、善意の名のもとに不透明な資金集めを行ったり、今回のように寄付や譲渡を装った金銭詐取に走る者も現れています。
このような行為は、まじめに活動している保護団体や獣医療関係者の信頼にも悪影響を与えかねません。寄付者や譲渡希望者が「また騙されるのではないか」と疑念を抱けば、社会全体の保護意識も萎縮してしまうのです。
読者へのお願いと注意喚起
動物を迎える際は、必ず「譲渡元の実体確認」を行ってください。信頼できる団体かどうか、事前の見学や面談を実施しているか、所在地や連絡先が明確かなどを確認することが、トラブルを避ける第一歩です。
また、寄付や費用負担を求められた際には、「具体的な使途」と「その妥当性」を慎重に見極めてください。不透明な説明や一方的な要求、急かすような連絡は、詐欺の典型的な特徴です。
悪質な例を目にするたびに、動物福祉に関わる立場として心を痛めています。こうした不正に対しては、警察や消費者センターへの通報、そしてSNSなどでの注意喚起が有効です。どうか、善意が裏切られる社会にならないよう、一人ひとりが冷静な目を持ち続けてください。