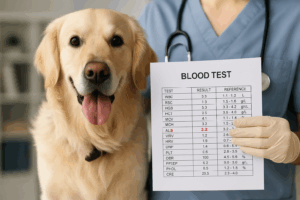「ワクチンのあとにぐったりしてしまった」「接種後すぐに苦しそうにしていた」――そんな経験や噂を耳にしたことはありませんか?
犬の健康を守るために行うワクチン接種ですが、まれに重篤なアレルギー反応「アナフィラキシー」を引き起こすことがあります。
また、この反応はワクチンだけでなく、一部の薬剤や昆虫の刺傷、食べ物などが原因で起こることもあります。
今回は、命に関わる可能性もあるこの疾患について、原因や症状、予防のポイントをわかりやすく解説します。
この記事はこんな方におすすめです
- 愛犬にこれからワクチン接種を受けさせる予定の方
- ワクチンや薬剤に不安を感じている方
- アナフィラキシーという言葉を聞いたことがあるが、詳しく知らない方
- 急な体調変化にどのように対応すべきか知っておきたい方
犬のアナフィラキシーとは
アナフィラキシーとは、短時間で全身に起こる急性の重度なアレルギー反応です。
正確には、免疫グロブリンE(IgE)という物質を介して起こる「即時型過敏反応(Ⅰ型アレルギー)」のうち、全身症状を伴うものを「アナフィラキシー」と呼び、特に命に関わるショック状態を「アナフィラキシーショック」と呼びます。
ただし、IgEを介さずに似たような症状が出る場合もあり、それを「アナフィラキシー様反応」と呼ぶことがあります。いずれにしても、緊急対応が必要であることに変わりはありません。
🔍 補足:IgEとは
体内に異物(アレルゲン)が入ったときに、免疫反応として働く抗体の一種です。これがマスト細胞を刺激し、ヒスタミンなどの物質が放出されることで、血管や呼吸器などに影響が出ます。
原因
アナフィラキシーは、一部のワクチン・薬剤・食べ物・昆虫の毒などが引き金となって発症します。
犬でよくみられる原因例:
- 混合ワクチン接種
- 抗生物質や麻酔薬
- ハチなどの虫刺され
- 食物(特定のタンパク質など)
- 造影剤などの医療用物質
アナフィラキシーの症状
症状は数分〜数時間で現れ、軽症から重症まで様々です。
代表的な症状:
- 顔や体の赤み・腫れ(浮腫)
- 呼吸困難(ゼーゼー、苦しそうにする)
- 嘔吐、下痢
- ぐったりして反応が鈍くなる
- 意識消失やショック症状(血圧の急低下など)
特に注意が必要なのは、ワクチン接種がきっかけとなるアナフィラキシーが比較的多く報告されていることです。
また、小型犬や純血種の犬ではアレルギー反応が起こりやすい傾向があり、実際にアナフィラキシーの症例はそうした犬種で多く見られます。
中でも、ミニチュアダックスフンドはアレルギー反応を起こしやすい犬種のひとつとされており、特に注意が必要です。
アナフィラキシーの診断
診断は、ワクチン接種や薬剤の投与後に特徴的な症状が現れることから、臨床的に判断されます。
アナフィラキシーには明確な検査法がないため、症状の出方や投与との時間的な関係性をもとに、迅速かつ的確な見極めが重要です。
アナフィラキシーの治療
アナフィラキシーは一刻を争う救急疾患です。以下のような治療が行われます:
- アドレナリン(エピネフリン)の注射:最も重要な初期対応。血圧の維持と気道確保に有効。
- 輸液:血圧低下を補正するために点滴で体液を補う。
- ステロイド薬(グルココルチコイド):炎症反応を抑える。
- 抗ヒスタミン薬:ヒスタミンによる過剰反応を抑える。
💡 ワンポイント
アナフィラキシーは発症の初期対応が命を左右します。自己判断せず、すぐに動物病院へ!
アナフィラキシーを経験したことのある犬では、今後のワクチンや薬剤の使用に特別な配慮が必要です。
あらかじめ獣医師と相談し、必要であれば事前に抗アレルギー薬を投与する、あるいは接種自体を見直すといった対策をとることで、再発のリスクを軽減することができます。
予後
治療が早期に行われれば、ほとんどの犬は回復が可能です。しかし、対応が遅れたり症状が重篤な場合には、命に関わることもあります。
また、一度アナフィラキシーを経験した犬は再発リスクが高まるため、今後の治療やワクチン接種には十分な注意が必要です。事前に獣医師と相談し、対応方針を決めておくと安心です。
まとめ
アナフィラキシーはまれではありますが、誰にでも起こり得る緊急事態です。特にワクチンや薬を使用する際には、「もしも」に備えた心構えが大切です。
接種や薬の投与後は、少なくとも30分程度は動物病院で様子を見てから帰宅することをおすすめします。また、過去にアレルギー反応を起こしたことがある犬については、事前に獣医師に相談し、対応をあらかじめ決めておくことが重要です。
さらに、アナフィラキシーの既往歴がある場合は、将来的なワクチン接種の見直しや、必要に応じて抗アレルギー薬の事前投与などを検討することも、予防の一環となります。
不安なことがあれば、かかりつけの獣医師に遠慮なく相談しましょう。早めの対応が、愛犬の命を守ることにつながります。