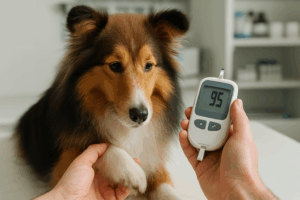動物病院での血液検査結果に「ALP」や「GGT(γ-GTP)」という項目があり、数値が高い・低いといった説明を受けて戸惑ったことはありませんか?
この記事では、犬の肝臓に関連する酵素のうち、特に「誘導酵素」と呼ばれるALPとGGTについて詳しく解説します。
愛犬の血液検査結果と照らし合わせながら、ぜひ参考にしてください。
・正常値は使用する検査機器や検査会社によって異なります。必ず検査結果用紙に記載された基準値を参照してください。
・検査結果が基準値を外れていても、必ずしも病気を意味するわけではありません。必ず担当獣医師の説明を受けましょう。
はじめに:犬の肝酵素にはどんな種類があるの?
犬の血液検査でよく見かける肝酵素には、主に4種類あります。
それが、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP(アルカリフォスファターゼ)、そしてGGT(γ-GTP、γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)です。これらの酵素は肝臓を中心にさまざまな組織に存在しており、肝臓や胆道系、さらに他の臓器の状態を把握するための大切な指標となります。これら肝酵素は、働き方や体内での動き方によって、大きく2つのタイプ(グループ)に分けることができます。
ひとつは「逸脱酵素」と呼ばれるものです。これは、肝臓やその他の細胞がダメージを受けて壊れることで血液中に漏れ出てくる酵素で、主にASTとALTが該当します。これらは細胞の障害や壊死が起きた際のサインとなります。
もうひとつは「誘導酵素」です。これは細胞が刺激を受けることで産生量が増え、血液中の濃度が上昇する酵素で、ALPとGGT(γ-GTP)がこれにあたります。胆汁の流れが滞った場合や、特定の薬剤による影響などで上昇するのが特徴です。
この記事では、この誘導酵素であるALPとGGT(γ-GTP)にスポットを当て、それぞれがどのような時に上昇するのか、異常値が示す意味について詳しく解説していきます。
ALP(アルカリフォスファターゼ)とは
ALPは体内のさまざまな組織に存在する酵素ですが、特に肝臓や胆道系、そして骨に多く含まれているのが特徴です。
この酵素は、胆汁の流れが滞る「胆汁うっ滞」のような状況や、骨の代謝が活発になる時に血液中の数値が上昇します。
胆汁うっ滞は、胆石や腫瘍、炎症などにより胆汁の流れが妨げられた際に起こり、ALPの上昇はこうした肝胆道系の異常を示す重要なサインとなります。一方で、骨の新陳代謝が活発な時期、特に子犬の成長期にもALPは自然と高値を示します。この場合は病的意義は少なく、むしろ正常な生理現象と考えられています。さらに、ALPはステロイド(グルココルチコイド)をはじめとする一部の薬剤によっても誘導され、上昇することが知られています。これは肝臓内の酵素産生が薬剤によって刺激されることで起こるため、病気による上昇とは必ずしも直結しないケースも多くみられます。
このように、ALPの上昇には病的な原因だけでなく、成長・薬剤・生理的要因など多様な理由が関与しているため、数値だけで一概に判断せず、他の検査結果や状況と合わせて慎重に評価することが大切です。
| 検査会社 | 基準値 |
|---|---|
| 富士フィルムモノリス | 49~298 IU/l |
| アイデックス(成犬) | 23〜212 IU/l |
ALP高値の原因
ALP高値の原因は、肝胆道系疾患と骨由来、そしてグルココルチコイド(ステロイド)誘発性などのその他の原因に分類されます。
| ALP高値の原因 |
| 肝胆道系疾患 急性/慢性肝炎 胆管炎/胆管肝炎 レプトスピラ症 トキソプラズマ 胆汁うっ帯 骨由来 原発性/転移性の骨腫瘍、 ビタミンD欠乏や代謝異常 原発性上皮小体機能亢進症 二次性上皮小体機能亢進症 骨の成長 その他の原因 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群) グルココルチコイド(ステロイド)の投与 糖尿病 抗てんかん薬の投与 |
ALP低値の原因
臨床的意義なし
γ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)とは
γ-GTP(γ-GGT、γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)は、ペプチドのN末端にあるグルタミン酸を他のペプチドまたはアミノ酸に転移する酵素であり、グルタチオンの生成に関与する重要な酵素です。
グルタチオンは、肝臓のミクロソームに存在し、薬物や有害物質の代謝・解毒に関与しています。つまり、肝機能を維持するうえで欠かせない物質の一つとされています。
このため、γ-GTPは肝細胞に多く存在し、肝疾患や胆道系の疾患では一般的に高値を示します。特に胆汁うっ滞性疾患では顕著な上昇がみられます。
また、ジアゼパムやフェノバルビタールなどの一部の薬剤は、肝臓内のミクロソーム酵素を誘導する作用があるため、これらの薬剤投与によってもγ-GTPの血中濃度が上昇することがあります。
また、GGTはALPと異なり、骨の代謝に関与していないため、骨疾患による上昇は見られません。
この特徴から、ALPとGGTを組み合わせて考えることで、上昇の原因が骨由来なのか、肝胆道系由来なのかを判断する重要な手がかりになります。
| 検査会社 | 基準値 |
|---|---|
| 富士フィルムモノリス | 3~12 IU/I |
| アイデックス(成犬) | 0〜11 IU/I |
γ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)高値の原因
γ-GTPは主に肝臓に存在するため、肝臓や胆道の異常で上昇します。特に胆汁の流れが滞る胆汁うっ滞性疾患では強く上昇します。また、薬剤による薬物性肝障害でもγ-GTPの上昇がみられます。
また、同じく肝胆道系疾患の指標としてよく使われるALP(アルカリフォスファターゼ)とは異なり、γ-GTPは骨疾患では上昇しないため、肝胆道に特異的なマーカーとして評価できます。
| γ-GTP(GGT)高値の原因 |
| 胆汁うっ滞 急性/慢性肝炎 肝硬変 肝臓の腫瘍 薬物性肝障害(ジアゼパム、フェノバルビタールなど) |
γ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)低値の原因
γ-GTPの低値に関しては、臨床的な意義はほとんどありません。
ALPとGGTを組み合わせてみることでわかること
ALPとGGTは、どちらも胆汁うっ滞時に上昇する誘導酵素ですが、同時に上昇している場合は、胆道系の疾患をより強く疑う根拠になります。
逆に、ALPが高くGGTが正常の場合は、ステロイドの影響や骨由来のALP上昇が考えられます。
このように、他の肝酵素(AST、ALT)や画像検査と組み合わせることで、より正確な診断が可能になります。
まとめ
犬の血液検査で測定される肝酵素(ALPとGGT)は、いずれも誘導酵素として、肝胆道系の状態を知るために欠かせない指標です。
ALPは肝臓や胆道系だけでなく骨にも存在するため、胆汁うっ滞や骨代謝の亢進(子犬の成長期や骨疾患など)でも上昇する酵素です。
また、ステロイドや一部の薬剤によっても増加する場合があり、必ずしも病気とは限らないケースも少なくありません。
一方、GGTは主に肝臓内の胆管に存在しており、胆汁うっ滞や薬物の影響によって上昇することが多い酵素です。
特にGGTは骨疾患では上昇しないため、ALPと組み合わせることで、肝胆道系疾患をより特異的に評価する上で役立ちます。
このように、ALPとGGTの両方を総合的に見ることで、肝胆道系の異常をより正確に捉えることが可能です。
ただし、いずれの数値も単独では病気の有無や重症度を判断することはできません。
異常値が認められた場合は、他の肝酵素(AST、ALT)、画像診断(レントゲン・超音波検査)、さらには血清総胆汁酸などの検査結果と併せて総合的に評価することが重要です。
愛犬の血液検査結果で気になる項目があった場合は、自己判断せず、必ず獣医師に相談し、適切なアドバイスと必要な検査を受けましょう。