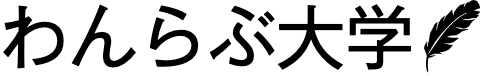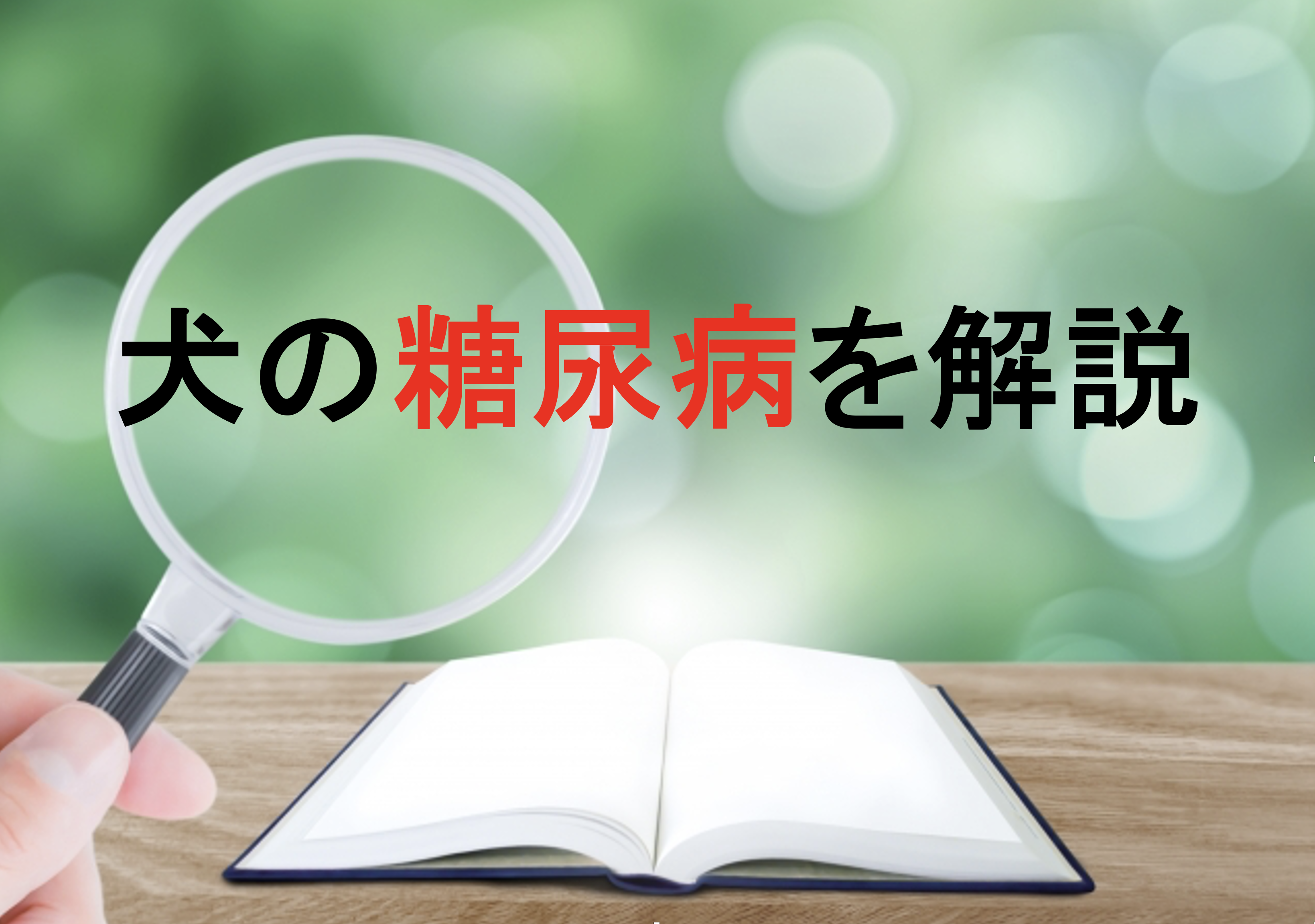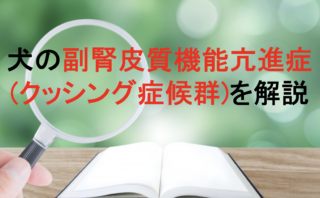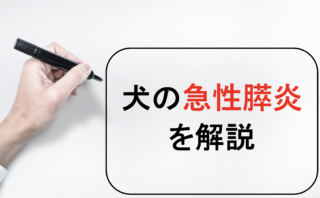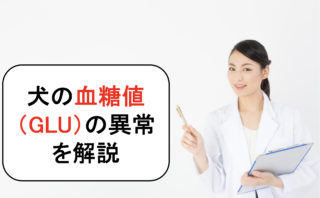この記事では、犬の糖尿病について原因、症状、診断そして治療を、現役獣医師が解説しています。
最後まで読むだけで、糖尿病について誰にでもすぐに理解できるように作成しているので、是非一度目を通していただけると嬉しいです。
犬の糖尿病とは
糖尿病とは、インスリンが十分に働かなくなり、血糖をうまく細胞に取り込めなくなる病気です。その結果、血糖値が高くなってしまいます。
インスリンとは、膵臓のベータ細胞で作られるホルモンです。食後に血液中のブドウ糖が増加すると、膵臓からインスリンが分泌され、その働きにより肝臓や筋肉などの細胞に送り込まれ、エネルギーとして利用されます。このようにインスリンには、血糖値を調整する働きがあります。
膵臓は胃の後ろにある臓器で、代表的な働きは①膵液という消化液を分泌し、その中の消化酵素で食べ物の消化を助ける、②インスリンなどのホルモンを分泌し、血糖値を一定濃度にコントロールすることです。
犬の糖尿病は、中齢〜高齢の犬に比較的多く発生します。メス犬の糖尿病発生率は、オス犬の約2倍であるといわれています。ミニチュアピンシャー、トイプードル、ダックスフンド、ミニチュアシュナウザー、ビーグルで好発傾向がみられます。
糖尿病は発見が遅いと、糖尿病性昏睡という状態になり死に至ることもあるので、早期発見が重要となります。
原因
人の糖尿病の原因は、①インスリン分泌不足と②インスリン抵抗性の2つのタイプがあると説明されており、この二つが影響して高血糖となると考えられています。
- インスリン分泌不足
膵臓の機能が低下して、十分なインスリンが作れなくなってしまう状態 - インスリン抵抗性
インスリンは十分な量が分泌されているけれども、効果を発揮できない状態。運動不足や食べ過ぎが原因で肥満になるとインスリンが働きにくくなります。
犬の場合はほとんどが「インスリン分泌不足」が原因で糖尿病が起こるとされており、人の1型糖尿病に相当するのではないかと考えられています。
糖尿病は、避妊手術をしていない雌犬に多く、副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)や膵炎に併発して起こることもあります。
これは、未避妊だと黄体期のプロジェステロンが、副腎皮質機能亢進症はグルココルチコイドの過剰産生によりインスリン抵抗性を引き起こすので、糖尿病になりやすいとされています。
糖尿病の症状
インスリンの欠乏による高血糖が原因で、尿中に糖が漏れ出します。それによって尿量が増え、水分を補うために、水をたくさん飲むようになる、いわゆる多飲多尿となります。
また初期には、食欲は増しているのに痩せてくるといった症状が認められます。そして次第に元気や食欲が低下し、下痢や嘔吐などの消化器症状が見られることもあります。
症状が進行すると、ケトン体という物質が血液中に蓄積する糖尿病性ケトアシドーシスという状態となり、著しい脱水と吐き気や嘔吐、そして頻呼吸と呼ばれる浅く速い呼吸がみられるようになります。
また、高血糖が持続することで、白内障などの合併症を引き起こします。糖尿病が原因で起こる白内障では、症状が急速に両眼で進行することが特徴的で、その割合は初診時で約60%・1年後では約75%といわれれています。このため、犬の糖尿病では白内障の有無や進行具合を確認し、必要に応じて治療を行う必要があります。
糖尿病の診断
血液検査で血糖値の上昇があり、尿検査で尿糖が出ていれば、糖尿病を強く疑っていきます。そして、フルクトサミンや糖化アルブミンといった、過去2週間の血糖値を反映する糖尿病マーカーの上昇が伴えば、確定診断となります。
また、尿検査でケトンが検出された場合には、糖尿病性ケトアシドーシスが考えられるので、犬の状態が悪化していることを示します。
血糖が上昇する病気として糖尿病以外には、副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)、膵炎そしてグルココルチコイド(ステロイド)などの投与による医原性などがあります。
糖尿病の治療
治療の目的は、①多飲多尿などの症状を改善させ、②糖尿病性ケトアシドーシスを防ぎ、③白内障などの続発症を予防する事です。そのためには、インスリン投与と食事管理が重要です。
インスリン投与
犬の糖尿病は、インスリンでの治療が必要となることがほとんどです。そのため、インスリンの投与を行います。また、脱水が認められることが多く、初期には点滴による治療が必要となり、重症例では入院して管理することもあります。
犬の糖尿病の場合ほとんどのケースで、生涯に渡るインスリンの投与が必要です。そのため通常、1日2回食事の度に家で飼い主さんにインスリン注射を打ってもらいます。
また、インスリン治療中には、過剰投与による低血糖症状が出る可能性がありますので注意しましょう。低血糖の症状として、元気低下、運動性低下、ふらつき、震え、発作に気をつけましょう。
血糖値は1日を通して100~300mg/dlの間にあることが望ましいです。この範囲に血糖値を管理できれば、多飲多尿などの症状はほとんどみられません。
インスリン投与後の定期的に血糖値を測定する、血糖曲線を作成することは、血糖の最低値とインスリン作用の持続時間を評価するのに有用です。
その結果、血糖値の最低値が低すぎる場合(80mg/dl以下)はインスリン投与量を減らし、最低値が高すぎる場合(180mg/dl以上)はインスリン投与量を増やします。インスリン作用時間が短すぎる場合には、インスリンの種類を長時間作用型へ変更します。
また、フルクトサミンや糖化アルブミンといった糖尿病マーカーの測定によって、血糖管理の状態を知ることができます。糖化アルブミンでは25%以下を、フルクトサミンでは450μmol/L以下目標とします。

食事管理
犬の糖尿病治療において食事の管理はとても重要です。食後の高血糖の予防とインスリンの使用量を減らす目的で高繊維食が推奨されています。
インスリンでの治療を実施する際には、カロリー計算をして毎日決められた量の食事を与えるようにしなければなりません。そのため決められた食事以外のものは、あげないようにしましょう。
インスリンの効きが悪い場合
インスリンを体重1kgあたり2.0単位(例:5kgの犬なら10単位)投与しても血糖値が下がらない場合には、インスリン抵抗性が存在すると考えられます。副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)や避妊手術を実施していない雌犬の発情は、インスリン抵抗性を引き起こす代表例です。適切に治療を行うことで、血糖値が管理できるようになります。
副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)
発情
グルココルチコイド(ステロイド)投与
肥満
高脂血症
慢性炎症(慢性膵炎、慢性腸炎、歯周病など)
慢性腎臓病
肝疾患
甲状腺機能低下症
褐色細胞腫
予後
発症から数ヶ月が最も死亡率が高いです。それ以降も生存していれば、比較的長生きすることが可能です。
しかし犬の糖尿病は、飼い主への負担が大きい病気です。治療方針について担当の獣医師とよく相談しましょう。
まとめ
犬の糖尿病について解説しました。糖尿病の代表的な症状は、水をたくさん飲んで、たくさんおしっこをする多飲多尿です。
もし、愛犬に多飲多尿の症状が見られたら、糖尿病の可能性があるので、早めに動物病院へ行くようにしましょう。