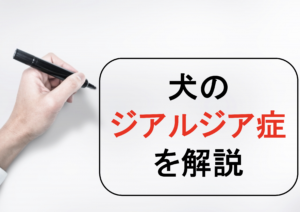愛犬の粘膜が白っぽく、体にあざのような皮下出血が見られる――
そんな異変に気づいたとき、飼い主さんは深刻な病気ではないかと心配になることでしょう。
なかでも「再生不良性貧血」は、血液をつくる機能そのものに問題が生じ、赤血球・白血球・血小板すべてが減少するという重篤な病気です。進行すると命に関わることもあり、早期発見と的確な治療が重要になります。
この記事では、犬の再生不良性貧血について、原因・症状・診断・治療・予後まで、現役の獣医師が丁寧に解説します。貧血や出血が気になる飼い主さん、また血液の病気について理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事はこんな方におすすめです
- 動物病院で「再生不良性貧血」と診断された、または疑われている犬の飼い主さま
- 元気がなく、出血や感染症が続いている犬に不安を感じている方
- 犬の血液疾患について学びたい獣医学生や動物看護師の方
再生不良性貧血とは
再生不良性貧血は、骨髄の中にある造血幹細胞が減少し、血液をつくる力そのものが低下することで起こる病気です。
その結果、赤血球・白血球・血小板のすべてが減少する「汎血球減少症」が引き起こされます。
造血幹細胞とは、赤血球・白血球・リンパ球・血小板など、すべての血液成分のもとになる細胞で、骨髄に存在しています。この幹細胞の働きが大きく損なわれるため、体内で新しい血液が十分に作れなくなってしまうのです。
なお、「再生不良性」という言葉から、「血液がうまく再生されない=非再生性貧血」のことと混同されがちですが、再生不良性貧血は“赤血球だけでなく、白血球・血小板も含めた3系統すべての血球が減少する状態”を指します。そのため、症状や治療のアプローチも、単なる貧血とは大きく異なります。
なお、同様に汎血球減少症を引き起こす病気として、骨髄異形成症候群(MDS)や悪性腫瘍の骨髄転移なども知られています。
原因
犬の再生不良性貧血には、原因が特定できない特発性と、明らかな要因がある二次性があります。
特発性(まれ)
- 自己免疫による骨髄破壊
- 遺伝子異常
- サイトカイン異常など
ただし、犬において特発性再生不良性貧血は非常に稀とされています。
二次性(多くはこれに該当)
- パルボウイルス感染症
- 骨髄抑制薬(抗がん剤など)
- 放射線障害
- エストロゲン過剰症(例:セルトリ細胞腫による)
再生不良性貧血の症状
再生不良性貧血では、以下のような血液成分の減少に伴う症状が現れます:
- 赤血球の減少 → 粘膜の蒼白・元気消失・呼吸促拍などの貧血症状
- 白血球の減少 → 発熱・下痢・咳・皮膚炎など感染症
- 血小板の減少 → 皮下出血・鼻出血・血尿・便に血が混じるなど出血傾向
初期は分かりにくくても、複数の症状が重なってくると進行した病気である可能性が高いです。
再生不良性貧血の診断
まずは血液検査を行い、汎血球減少症の有無を確認します。以下のような特徴がみられる場合には、再生不良性貧血が強く疑われます。
- 赤血球・白血球・血小板のすべてが減少している
- 赤血球の再生がみられない(非再生性貧血)
なお、人の医学分野では、赤血球・白血球・血小板のうち2系統以上の減少が認められた場合に、再生不良性貧血の診断基準に該当するとされています。犬でも、これら複数の血球の減少が重要な診断の手がかりとなります。
再生不良性貧血の確定診断には、骨髄生検(コア生検)が必要です。検査の結果、骨髄の95%以上が脂肪に置き換わっている「脂肪髄」が確認される場合、この病気に特徴的な所見とされます。
再生不良性貧血の治療
治療の基本は、原因に応じた対処と対症療法です。
対症療法
- 輸血(貧血や出血の改善)
- 抗菌薬(白血球減少による感染対策)
造血刺激療法
- エリスロポエチンやG-CSFの投与により、一時的に血球数の改善が期待される場合もあります
原因療法
- 二次性であれば、基礎疾患(例:腫瘍・感染症など)の治療が必要です
- ただし、骨髄破壊が不可逆的な場合は治療効果が乏しいことも多く見られます
免疫抑制療法
- ステロイドや免疫抑制剤が使用されることもありますが、有効性は不明確です
予後
犬の再生不良性貧血は予後が非常に悪いとされる病気のひとつです。
現時点で根本的な治療法は確立されておらず、幹細胞移植などの先進医療の進展が期待されています。
まとめ
犬の再生不良性貧血は、血液を構成する全成分が減少してしまう重篤な病気であり、感染や出血などさまざまな症状を引き起こします。
犬の場合は二次性のケースが多いため、原因疾患を早期に発見・治療することが非常に重要です。
症状に気づいたら、すぐに動物病院を受診し、早めの診断と適切な対応を受けるようにしましょう。