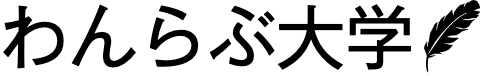動物病院で血液検査を行った際に、その結果を理解するための手助けとなるように記事を作成しました。愛犬の血液検査の結果を片手にご覧ください。
ただし、以下の点にご注意ください。
- 正常値は、機械や検査会社ごとによって異なりますので、血液検査に記載されているデータを参照してください。
- 検査結果が基準値(正常値)を外れている場合でも、病気とは限らないので、担当の獣医さんに良く話を聞くようにしましょう。
赤血球数(RBC),ヘモグロビン(Hb),ヘマトクリット(HCT)とは
赤血球とは、血液循環によって体中を回り、肺から得た酸素を体の隅々の細胞に供給する役割を担い、また同様に二酸化炭素の排出も行う血液細胞の一つです。
赤血球は骨髄で産生され、その寿命は約120日であり、古くなると脾臓や肝臓で処理されます。
また、赤血球の増殖にはエリスロポエチンという物質が大きく関わります。エリスロポエチンは、貧血や慢性の心肺疾患、空気の薄い高地での生活などで慢性の低酸素状態になると、腎臓から盛んに分泌され、赤血球を増加させます。このことから、エリスロポエチンは増血因子と呼ばれます。
ヘモグロビンとは、赤血球細胞質の主要な構成物質であり、肺から全身へ酸素を運搬する役割を担っているタンパク質です。
ヘマトクリットとは、血液中に存在する赤血球の容積の割合を示しています。またPCVとは、血液中の血球成分の容積の割合を示しています。通常は、血球成分の大部分が赤血球なのでヘマトクリット=PCVと考えて差し支えないかと思います。
ふつう、赤血球数が増えると、ヘモグロビン量も増え、ヘマトクリットも上がります。逆に、赤血球数が減ると、ヘモグロビン量は減り、ヘマトクリットも下がります。このように、3つの値は密接に関係して増えたり減ったりします。
赤血球が異常に増えてしまう疾患のことを多血症または赤血球増加症と呼び、赤血球が少なくなる疾患のことを貧血と呼びます。
| 検査会社 | RBC | Hb | HCT |
|---|---|---|---|
| 富士フィルムモノリス | 550〜850×10⁴/μl | 12.0〜18.0 g/dl | 37.0〜55.0 % |
| アイデックス | 5.65〜8.87×106/μl | 13.1〜20.5 g/dl | 37.3〜61.7 % |
多血症(赤血球増加症)の原因
多血症(赤血球増加症)の原因は、血液中の液体成分が減少した事による見かけ上の赤血球数の増加による相対的増加の場合と、何らかの原因に反応して実際に血液中の赤血球総数が増加する絶対的増加の場合があります。
犬の血液検査で最もよくみられる多血症の原因は、脱水による相対的な増加です。
相対的増加の原因
血液中の液体成分が減少した事による見かけ上の赤血球数の増加によるものです。
脱水
出血性胃腸炎
絶対的増加の原因
何らかの原因で、造血因子であるエリスロポエチンの量が増えるために赤血球数の増加が起こる「二次性赤血球増加症」と、骨髄での赤血球の産生が増える「真性赤血球増加症」があります。
さらに二次性赤血球増加症には、慢性的な酸素欠乏による反応性によるものと、腎臓腫瘍によるエリスロポエチンの過剰産生によるものがあります。
※エリスロポエチン:赤血球の産生を促進する造血因子で、主に腎臓で作られます。
二次性赤血球増加症
慢性的な酸素欠乏(心疾患、呼吸器疾患、高地居住など)
エリスロポエチンを過剰産生するタイプの腎臓の腫瘍
真性赤血球増加症
腫瘍(真性多血症など)
貧血の原因
貧血には赤血球の破壊や喪失が原因で骨髄には原因がない「再生性貧血」と、骨髄での造血機能の低下を原因とする「非再生性貧血」とがあります。
再生性貧血なのか非再生性貧血なのかは、MCV、MCH、MCHCの値によって概ね予測が可能です。また併せて、顕微鏡で赤血球の観察を行い貧血の特徴を捉えます。
再生性貧血
赤血球の破壊や喪失が原因で骨髄には原因がない貧血
非再生性貧血
骨髄での造血機能の低下を原因とする貧血
赤血球恒数(MCV,MCH,MCHC)とは
MCV(平均赤血球容積)、MCH(平均赤血球ヘモグロビン量)、MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度)は赤血球恒数といい、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリットの値から算出します。
具体的には、以下のように計算されます。
MCV(平均赤血球容積):[ヘマトクリット値(%)÷赤血球数(106/㎣)]×10 MCH(平均赤血球ヘモグロビン量):[ヘモグロビン(g/㎗)÷赤血球数(106/㎣)]×10 MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度):[ヘモグロビン(g/㎗)÷ヘマトクリット値(%)]×100
貧血には様々な要因があるので、その種類(原因)を絞り込むための検査項目となります。
| 検査会社 | MCV | MCH | MCHC |
|---|---|---|---|
| 富士フィルムモノリス | 60.0~77.0fL | 19.5〜26.0pg | 32.0~36.0% |
| アイデックス | 61.6~73.5fL | 21.2~25.9pg | 32.0~37.9% |
大球性低色素性貧血(MCVの高値、MCHCの低値)
再生性貧血全般
正球性正色素性貧血(MCV正常、MCHC正常)
非再生性貧血一般
小球性低色素性貧血(MCV低値、MCHC低値)
鉄欠乏性貧血
大球性正色素性(MCV高値、MCHC正常)
赤血球成熟異常
赤芽球系の腫瘍
まとめ
犬の赤血球系の異常である多血症(赤血球増加症)と貧血について解説しました。
検査結果が正常値を外れている場合でも、必ずしも病気とは限りません。病気は、血液検査のみならず身体検査や他の検査も行って診断していきます。状況により、経過観察を行ったりさらに詳しい検査を行うことがあります。
多血症(赤血球増加症)時には、まず脱水がないかをチェックします。脱水がないにも関わらず多血症と判断されれば、追加検査としてレントゲン検査、超音波検査そしてエリスロポエチンの測定などを行います。
また貧血時には、まず再生性貧血か非再生性貧血かの判断を行います。それによって追加検査として、レントゲン検査、超音波検査そして尿検査などを行います。
血液検査の結果で心配な事がある時には、動物病院で獣医さんに遠慮なく質問してみましょう。