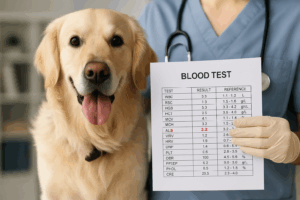動物病院で血液検査を受けた際に、検査結果をより深く理解するためのサポートとしてこの記事を作成しました。
愛犬の血液検査結果をお手元に置きながら、ぜひご覧ください。
※正常値は検査機関や機器によって異なるため、必ず検査結果に記載された基準値を参考にしましょう。
※また、基準値を外れていても必ずしも病気というわけではありません。獣医師とよく相談することが大切です。
炎症マーカー(CRP)とは
炎症マーカーとは、体内に炎症が存在するか、またその程度を反映する検査のことを指します。
中でも代表的なものがCRP(C-reactive protein:C反応性タンパク質)であり、犬の血液検査でも広く用いられています。
CRPは、炎症が起こると炎症性サイトカイン(IL-6など)の刺激を受けて、主に肝臓で合成されます。
炎症が発生してからおよそ6時間後からCRPの血中濃度が上昇しはじめ、24〜48時間以内にピークに達します。
CRPは他の急性相タンパクと比べて反応性に優れており、
平常時の100倍から1000倍に達することもあります。
また、半減期は数時間〜12時間程度と短く、炎症が治まると速やかに低下します。
加えて、CRPは興奮や運動の影響を受けにくいという特徴もあります。
このため、CRPを測定することで、炎症の有無やその程度を客観的かつ迅速に把握することが可能となります。
炎症マーカー(CRP)が役立つ場面
- 「なんとなく元気がない」といった曖昧な症状に対するスクリーニング
- 治療中の経過観察や、治療終了のタイミング判断
CRPを参考にすることで、治療を早期に中止しすぎたり、逆に不必要に長引かせたりするリスクを減らすことができます。
| 検査会社 | 基準値 |
|---|---|
| 富士フィルムモノリス | 0.7mg/dl以下 |
| アイデックス | 0.0〜1.0mg/dl |
高値を示す場合
炎症性疾患、感染症、腫瘍が存在する場合には、CRPが高値を示すことが多く、
特に全身に影響を及ぼすような疾患では、顕著な上昇が認められます。
具体的には、感染性あるいは炎症性疾患として
子宮蓄膿症、特発性多発性関節炎、無菌性結節性脂肪織炎などが挙げられ、
また腫瘍では、血管肉腫やリンパ腫の症例において高い割合でCRPの上昇が認められます。
さらに、免疫介在性溶血性貧血やバベシア症といった血液疾患・寄生虫感染症でも、CRPの上昇が報告されています。
一方で、膀胱炎、鼻炎、平滑筋肉腫のように病変が比較的限局している疾患では、
CRPの大きな上昇はあまり認められないとされています。
中枢神経に関わる炎症性疾患、
たとえば壊死性髄膜脳炎や肉芽腫性髄膜脳炎においても、
通常はCRPの上昇はみられません。
ただし例外的に、ステロイド反応性髄膜動脈炎では、
中枢神経系疾患の中でも特異的にCRPの高値が認められることが知られています。
まとめ
犬の血液検査における炎症マーカー(CRP)について解説しました。
CRPの値が基準を外れていても、それだけで病気の確定診断には至りません。
血液検査結果は、身体検査や画像検査(レントゲン検査、超音波検査など)、尿検査と組み合わせて総合的に判断する必要があります。
また、炎症の指標には白血球数もありますが、
| 比較項目 | 白血球数 | CRP |
|---|---|---|
| 反応速度 | 数時間以内に上昇 | 6〜12時間後から上昇 |
| 炎症以外の影響 | 強く受ける(興奮・ストレス等) | ほとんど受けない |
という違いがあり、それぞれの特性を理解して使い分けることが大切です。
血液検査の結果について心配なことがあれば、遠慮せずに獣医師に質問してみましょう。