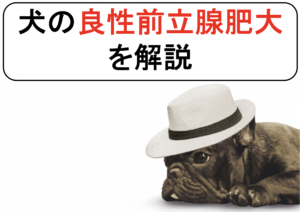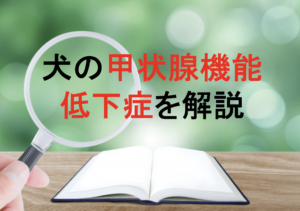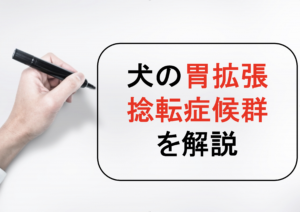この記事では、犬のリンパ腫について原因、症状、診断そして治療を、現役獣医師が解説しています。
最後まで読むだけで、リンパ腫について誰にでもすぐに理解できるように作成しているので、是非一度目を通していただけると嬉しいです。
リンパ腫とは
リンパ腫は、白血球の一種であるリンパ球が腫瘍化したものです。リンパ系組織(リンパ節、リンパ管、脾臓、胸腺、扁桃など)で発生する悪性腫瘍です。
リンパ系とは、リンパ液と呼ばれる清明な液を運搬する導管ネットワークであり、リンパ液が通過するリンパ節などのリンパ組織もこれに含まれます。
リンパ系には3つの働きがあります。①組織から組織液を取り除く働き、②吸収された脂肪酸と脂質を乳糜(にゅうび)として循環系まで運ぶ働き、③単球や抗体産生細胞などのリンパ球をはじめとする免疫細胞を産生する働きです。
犬のリンパ腫では、発生部位や腫瘍細胞の形態により分類が行われます。
- 発生部位による分類:発生部位によって、多中心型(リンパ腫全体の80%)、縦隔型(5%)、消化器型(5%)、その他(10%)に分類されます。
- 形態による分類:腫瘍細胞の形態によって、低分化型リンパ腫(別名:高悪性度リンパ腫)と高分化型リンパ腫(別名:低悪性度リンパ腫)に分類されます。
リンパ球は、T細胞とB細胞に分類されます。両者の違いは以下の通りです。
- T細胞:胸腺由来で細胞性免疫に関与している
- B細胞:骨髄由来で液性免疫に関与している
犬のリンパ腫では、T細胞が腫瘍化しているか、B細胞が腫瘍化しているかによって、症状や予後に違いが生じてきます。
好発年齢はありませんが、6〜8歳での発生が最も多いといわれています。雄犬と雌犬での発生の差は無く、好発犬種は特にありません。
ただし、ミニチュアダックスは例外的で、以下の特徴があります。
- 比較的若齢で発生する
- 雄での発生が多い
- 消化器型リンパ腫が多い
- 生存期間が長い
原因
はっきりとした原因はわかっていませんが、何らかの遺伝子の異常によって発生するものと考えられています。
以下の要因が、リンパ腫を引き起こす可能性が示唆されています。
- 除草剤
- 強力な磁場の影響
- 都市部に住む犬であること
リンパ腫の症状
リンパ腫の症状は、発生部位により異なります。
多中心型リンパ腫
犬で最も多くみられるタイプのリンパ腫です。全身の皮膚の下にあるリンパ節が左右対称性に大きくなるのが典型的な症状です。
リンパ腫が発症しても、初期は元気で症状がみられないことも多いです。しかし、徐々に元気や食欲が低下してきます。さらに、顎や喉の周りのリンパ節が腫れることにより、呼吸がゼーゼーしたりイビキが目立つ場合もあります。

消化器型リンパ腫
消化器型リンパ腫は、犬の消化管に発生する腫瘍の中で最も多い腫瘍です。T細胞が腫瘍化したものが多いです。
慢性嘔吐、慢性下痢、食欲不振、体重減少などが典型的な症状です。


消化器型リンパ腫の発生がよくみられる部位は、以下の通りです。
- 小腸での発生が最も多い
- 胃と結腸がそれに続く
中齢〜高齢の犬での発症が多いです。しかし、若齢での発症が認められる場合もあります。
消化管に腫瘤を作るタイプやお腹のリンパ節が腫れている場合には、お腹を触診すると腫瘤が触れることがあります。
腫瘤(しゅりゅう)とは、病気の種類が何であれ、体や臓器の一部に塊が生じている状態
リンパ腫の診断
低分化型リンパ腫(高悪性度リンパ腫)では、針生検で確定診断が可能です。
細い針で細胞を取って顕微鏡で観察する検査
リンパ球クローン性検査という遺伝子検査が、補助的に用いられます。これは、腫瘍細胞がT細胞かB細胞かの判断を行う検査です。
T細胞が腫瘍化したリンパ腫では、血液検査で高カルシウム血症がみられる場合があります。

多中心型リンパ腫
低分化型リンパ腫(高悪性度リンパ腫)と高分化型リンパ腫(低悪性度リンパ腫)で診断方法が異なります。
- 低分化型リンパ腫(高悪性度リンパ腫):針生検で診断が可能
- 高分化型リンパ腫(低悪性度リンパ腫):リンパ節の摘出手術による検査が必要な場合がある
その他の検査として、血液検査やントゲン検査や超音波検査などの画像検査を行います。それぞれの検査で、以下の確認を行います。
- 血液検査:血液中にリンパ腫の細胞がないか確認する
- 画像検査(レントゲン検査や超音波検査):体の中のリンパ節や臓器の異常の有無を確認する
消化器型リンパ腫
診断は、血液検査や超音波検査を行い、針生検を実施します。
血液検査では、多くの場合低アルブミン血症がみられます。
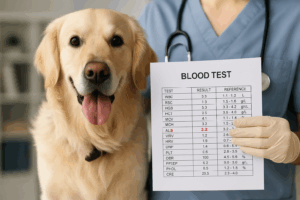
超音波検査では、以下の異常所見がみられます。
- 消化管の肥厚や層構造の消失
- 腸間膜リンパ節の腫大
しかし、約3/4の犬の消化器型リンパ腫では、超音波検査で異常が認められなかったと報告されています。この場合には、以下の方法で確定診断を行います。
- 内視鏡生検を行い病理組織学的検査を実施する
- 開腹して消化管の一部を切除し、病理組織学的検査を実施する
リンパ腫の治療
低分化型リンパ腫(高悪性度リンパ腫)と高分化型リンパ腫(低悪性度リンパ腫)で治療方針が異なります。
リンパ腫の主な治療は、化学療法です。化学療法は、いくつかの抗がん剤を組み合わせた治療が主体です。
化学療法剤(抗がん剤、化学物質)を使って、がん細胞の増殖を抑えたり破壊したりすることによる治療
多中心型リンパ腫
低分化型リンパ腫(高悪性度リンパ腫)では、1~2週間に1回抗がん剤を注射する治療を6ヶ月程度継続する化学療法が主流です。この治療で約90%の犬が、普通のリンパ節の大きさに戻り、元気に過ごすことができるようになります。
これを寛解と呼びます。寛解状態の期間は様々ですが、ほとんどの犬で再発が見られます。
病気の症状がほぼ消失した状態。病気が完全に治った治癒とは異なる。
リンパ腫の再発時には、多くは抗がん剤が効きにくくなっています。これが再発時の問題となります。
治療を行った場合の生存期間の中央値は、約1年といわれています。時に、2年以上生存する場合もあります。初回の治療に反応しない場合、早期に亡くなる傾向があります。
低分化型リンパ腫(高悪性度リンパ腫)で治療を行わない場合、1ヶ月以内で死亡するとされています。
高分化型リンパ腫(低悪性度リンパ腫)では、以下の3項目を評価します。いずれの項目もみられなければ、無治療で経過観察を行います。
- リンパ節が大きくなることによる呼吸困難などの症状
- 元気食欲などの一般状態の低下
- 血球減少症(貧血、好中球減少症、血小板減少症)
この3項目のいずれかに異常が認められた場合、治療を行います。
消化器型リンパ腫
化学療法が治療の中心となります。
化学療法の生存期間の中央値は、77日と報告されています。これは、多中心型リンパ腫の生存期間と比べると短いです。
直腸に発生した消化器型リンパ腫は、化学療法や外科手術などの治療を行った場合の平均生存期間は1,697日であったと報告されています。直腸に発生したリンパ腫は、B細胞性が多く、胃腸管リンパ腫と大きく異なる可能性が示唆されています。
まとめ
犬のリンパ腫について解説しました。最も多い多中心型リンパ腫では、リンパ節が腫れているのに気が付いたら全身のリンパ節を触って見ましょう。リンパ節が腫れるような他の病気がない場合には、リンパ腫の可能性があります。
リンパ腫の治療法は、いくつかの抗がん剤を組み合わせた化学療法が主体となりますが、多くの治療法があります。どの治療法を選択するかについて副作用なども含めて、獣医師さんとよく相談されるとよいでしょう。