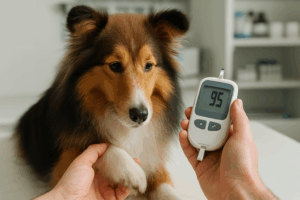動物病院で行う尿検査は、泌尿器疾患はもちろん、全身の健康状態を知るためにも非常に重要な検査です。
この記事では、尿検査でわかることや検査項目の意味について、飼い主の皆さまが愛犬の検査結果をより深く理解できるよう、詳しく解説します。お手元の尿検査結果と照らし合わせながらご覧ください。
ご注意ください
・尿検査の正常値は検査機器や検査会社によって異なります。必ず検査結果に記載された基準値を参照してください。
・基準値から外れていても必ずしも病気とは限りません。不明な点は獣医師に相談しましょう。
尿検査とは
尿検査は、腎臓や尿路といった泌尿器だけでなく、代謝や内分泌系など全身の異常の兆候をとらえる重要な検査です。
尿の採取方法
尿は以下の方法で採取されます。
- 自然排尿(最も一般的)
- カテーテル尿(細菌や細胞の混入が少ない)
- 膀胱穿刺尿(最も混入リスクが低い)
自然排尿でも十分な情報は得られますが、細胞や細菌の混入リスクがあるため、より正確な検査が求められる場合はカテーテルや膀胱穿刺が選ばれます。
採尿後は、冷蔵保存で6時間以内の検査が推奨されますが、低温によって結晶が析出する可能性がある点には注意が必要です。

尿の性状(外観や臭い)
視覚・嗅覚を用いて尿の色、濁り、臭いを観察する官能検査です。
色
- 黄色が濃い → 尿の濃縮(脱水など)
- 黄色が薄い・透明 → 尿が希釈(多飲多尿など)
- 赤色尿 → 出血、溶血、ミオグロビン尿の可能性(出血の場合は尿が濁る傾向あり)
- 緑がかった尿 → ビリルビン増加の可能性
清濁
- 白濁 → 膿尿、結晶、脂肪分の増加など
臭気
- 悪臭 → 膿尿が疑われる
尿比重
尿比重は腎臓の濃縮・希釈能力や水分状態を評価する重要な指標です。
- 正常濃縮 → 1.030以上
- 過剰濃縮(異常高値) → 1.050以上(脱水などが原因)
- 等張尿 → 1.008〜1.012(慢性腎不全の疑い)
- 低比重尿 → 1.007以下(希釈機能は働いているが慢性腎不全の可能性も)
尿比重がいつも低めであれば、腎機能障害が疑われるため注意が必要です。
尿定性検査
尿試験紙を用いて、pH、蛋白、糖、潜血、ビリルビン、ケトン体などの項目を簡便に評価する方法です。
検査時は尿の色(着色尿)によって偽陽性が生じる場合があるため、判定時間を守りつつ、慎重に読み取る必要があります。
pH
犬の尿pHの正常値は6.0〜7.0が一般的です。
- 酸性尿
肉食中心の食餌や、アシドーシス(代謝性・呼吸性)、発熱、飢餓、持続的な運動などによって生じます。
これらはタンパク質代謝の亢進や有機酸の蓄積が関与しています。 - アルカリ尿
植物食主体の食餌、膀胱内での尿貯留(尿閉、排尿困難など)、細菌性膀胱炎(尿素分解菌によるアンモニア産生)、アルカローシス(代謝性・呼吸性)などでみられます。
特に細菌感染(尿素分解菌)によるアルカリ化は、ストルバイト結石(リン酸アンモニウムマグネシウム結晶)形成のリスクになるため、状況によっては食事管理などで尿を酸性に保つ治療が必要です。
尿蛋白
正常では陰性ですが、尿比重が高い濃縮尿(1.050以上)では1+程度の陽性が出ても必ずしも異常とは言えません。
- 持続的蛋白尿
腎疾患(糸球体疾患によるアルブミン漏出、尿細管障害による再吸収低下)や尿路感染症が考えられます。
特に糸球体疾患では選択的アルブミン尿が中心です。 - 一過性蛋白尿
激しい運動、けいれん(てんかん発作)などによる血流動態や代謝の変化で、一過性に生じる場合もあります。
尿潜血
正常は陰性です。
- 陽性 → 尿中に赤血球、ヘモグロビン、またはミオグロビンが存在することを示します。
尿を遠心分離して再検査し、沈渣で赤血球が確認されれば血尿(尿路出血)、
赤血球が確認されず、それでも陽性であれば、溶血性疾患によるヘモグロビン尿や筋肉疾患によるミオグロビン尿が考えられます。
最も頻度が高いのは尿路感染症による血尿です。
ビリルビン
通常は陰性ですが、尿比重が1.020以上の濃縮尿では、1+程度の陽性は正常範囲内とされます。
- 陽性 → 肝胆道系疾患(肝細胞障害、胆汁うっ滞)や溶血性疾患(ヘモグロビンの崩壊亢進)を示唆します。
ビリルビン尿は、血中ビリルビン濃度が上昇してから尿中に出現するまでが比較的早いため、黄疸が肉眼的に確認される前に異常の早期指標となる重要な所見です。
尿糖
正常は陰性です。
- 陽性 → 血糖値が腎閾値(通常は180〜220mg/dl程度)を超えた場合(糖尿病など)、または腎尿細管での再吸収障害(腎性糖尿)が考えられます。
尿糖が検出された場合、まずは血糖値を測定して高血糖の有無を確認することが重要です。
高血糖を伴わない尿糖はまれですが、先天性または後天性の尿細管障害(Fanconi症候群など)による腎性糖尿が疑われます。
また、尿路出血でも尿糖が偽陽性になる場合がありますので注意が必要です。
ケトン体
正常は陰性です。尿試験紙では主にアセト酢酸が検出されます(β-ヒドロキシ酪酸は検出されません)。
- 陽性 → 糖尿病(特に糖尿病性ケトアシドーシス)、飢餓、絶食、重度の低栄養状態など、糖以外の代替エネルギー源として脂肪が過剰に分解されている状態を示唆します。
ケトン体は肝臓で脂肪酸から産生され、エネルギー源として利用されますが、糖の利用障害や不足時に多量に生成・排泄されます。
ウロビリノーゲン
近年では犬の尿検査においてウロビリノーゲンの測定意義はほとんどないとされ、通常は評価対象外とします。
以上のように、尿定性検査では様々なパラメーターを組み合わせて判断し、尿中の成分異常の背景にある病態を推測します。
異常値がみられた場合でも、単独の結果のみで病気を断定せず、総合的な診断が必要です。
尿沈渣
尿沈渣とは、尿を遠心分離して沈殿した成分を顕微鏡で観察する検査です。
これにより、尿中に含まれる赤血球や白血球、結晶、細胞などの異常の有無や種類を詳しく調べることができます。
尿検査の中でも、より詳細な情報が得られる重要な検査です。

▲尿沈渣は遠心分離機を使って作成します
尿沈渣とは、尿を遠心分離して沈殿した成分を顕微鏡で観察する検査です。
これにより、尿中に含まれる赤血球や白血球、結晶、細胞などの異常の有無や種類を詳しく調べることができます。
尿検査の中でも、より詳細な情報が得られる重要な検査です。
赤血球
尿中に赤血球(血液の細胞の一つ)が含まれている場合は、尿路のどこかで出血が起きている可能性があります。
原因として多いのは膀胱炎や尿路結石などによる刺激や損傷です。
また、赤血球が尿中で溶けている場合(溶血)は、他の原因も考えられます。
白血球
尿に白血球が出ている(膿尿)場合は、尿路で炎症や感染が起きているサインです。
膀胱炎や腎盂腎炎などが疑われます。
尿円柱(にょうえんちゅう)
尿円柱は、腎臓内の尿細管でタンパク質や細胞成分が固まってできた細長い構造物です。
種類によって示唆する病態が異なります。
- 硝子円柱 → 健康な犬でも見られることがありますが、増加している場合は腎障害の可能性。
- 顆粒円柱 → 腎臓の炎症や障害を示唆します。
- 赤血球円柱 → 腎臓内での出血(糸球体腎炎など)を示します。
- 白血球円柱 → 腎盂腎炎など腎臓の感染を示します。
- 蝋様円柱 → 重度の慢性腎障害でみられることがあります。
尿円柱は腎臓の状態を反映する重要な指標です。
結晶
尿中の結晶は、尿のpHや成分バランスによって自然にできることもありますが、結石の前段階となることもあります。
- アルカリ尿でみられやすい結晶
┗ リン酸アンモニウムマグネシウム(ストルバイト)、尿酸アンモニウム、リン酸カルシウムなど - 酸性尿でみられやすい結晶
┗ シュウ酸カルシウム、尿酸塩など - 代謝異常と関連する結晶
┗ シスチン、チロシン、ロイシン、コレステロールなど(まれですが病気のサインになる)
尿中の結晶は、食事内容や水分摂取量などによっても変化するため、継続的な観察と総合判断が重要です。
細胞成分
尿中に上皮細胞が認められる場合、尿路(尿道・膀胱・腎盂など)の粘膜に何らかの刺激や障害がある可能性があります。
また、まれですが悪性腫瘍が疑われる異型細胞が検出されることもあります。
この場合は追加の検査(細胞診や画像診断など)が必要です。
尿沈渣の検査は、このように尿中に含まれる様々な成分を詳しく観察することで、泌尿器の健康状態や腎臓のトラブル、結石のリスクなどを把握する大切な手段です。
異常があった場合は、獣医師と相談の上で追加検査や治療方針を決めていきましょう。
まとめ
犬の尿検査は、腎臓や尿路の健康状態だけでなく、全身の異常の兆候を捉えるためにも欠かせない検査です。
尿検査の結果が正常値を外れていても、それが直ちに病気を意味するとは限りません。尿検査結果は身体検査や他の検査と併せて総合的に判断する必要があります。
異常がみられた場合は、追加で以下のような検査を行うケースもあります。
- 血液検査
- レントゲン・超音波などの画像検査
- 尿蛋白/クレアチニン比などの特殊検査
愛犬の健康を守るため、尿検査で気になる結果が出た場合は、遠慮せず担当獣医師に相談し、適切なアドバイスと今後の検査・治療方針を確認するようにしましょう。