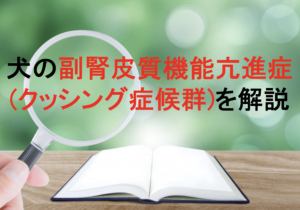「“ショック状態”です」――そんな言葉を獣医師から告げられたら、多くの飼い主さんは戸惑うことでしょう。
日常会話で使われる「ショック」とは異なり、医学的な「ショック」とは命に関わる重大な状態を指します。
この記事では、犬における「ショック(循環性ショック)」について、原因、症状、診断法、治療法、そして予後までをわかりやすく解説します。
この記事はこんな方におすすめです
- 犬がぐったりして意識がもうろうとしているなどの症状が出て心配な方
- 「ショック」と診断されたが、何が起こっているのかわからない飼い主さん
- 犬の救急疾患について知っておきたい方
- ショックの初期対応や予後について理解を深めたい方
ショックとは
医学的な「ショック」は、血圧の急激な低下により全身の臓器に酸素が届かなくなり、命の危機に陥っている状態です。
単なる驚きや恐怖といった感情ではなく、重度の循環不全による臓器障害を伴う、緊急かつ重篤な症候群です。
医学的には「循環性ショック」または「末梢循環不全」とも呼ばれます。
原因
ショックにはいくつかの分類があります。主なものは以下の3タイプです:
| 分類 | 原因の例 |
|---|---|
| 血液量減少性ショック | 出血、火傷、脱水、重度の下痢や嘔吐 |
| 心原性ショック | 心筋症、不整脈、心不全など心臓のポンプ機能低下 |
| 血液分布異常性ショック | アナフィラキシー、敗血症、熱中症などによる血管拡張 |
これらのいずれも、全身の血液循環が破綻し、酸素や栄養が臓器に届かなくなることで臓器障害が進行します。
ショックの症状
犬におけるショックの症状は、以下のような全身状態の急激な悪化として現れます:
- ぐったりして動かない(虚脱)
- 呼吸が浅く早くなる
- 脈拍が弱く触れにくい(微弱脈)
- 歯ぐきが白っぽくなる(粘膜蒼白)
- CRT(毛細血管再充満時間)が延びる(2秒以上)
- 意識がもうろうとする、不穏・興奮
- 体温が異常に低い(37.8℃以下)または高い(39.7℃以上)
💡 人におけるショックの典型的な症状には、顔面蒼白、虚脱(きょだつ:極度の脱力状態)、冷汗、脈拍触知不能、呼吸不全などが知られています。
⚠️ 血圧の低下は「収縮期血圧が90mmHg未満」あるいは「基礎値から40mmHg以上の急激な低下」が目安とされますが、動物では正確な血圧測定が難しいこともあるため、視診・触診・聴診などを総合して判断します。
ショックの診断
ショックの診断は、血圧の低下(収縮期血圧が90mmHg未満あるいは基礎値より40mmHgを超える減少)に加え、以下の6つの症状のうち3項目以上が確認されることが基準とされています:
- 心拍数160回/分以上
- 微弱な脈拍
- 毛細血管再充満時間(CRT)の延長
- 意識障害、または不穏・興奮状態
- 乏尿または無尿
- 体温が37.8℃以下または39.7℃以上
💡 CRTとは?
CRT(Capillary Refill Time:毛細血管再充満時間)とは、歯ぐきなどの粘膜を指で一時的に圧迫し、白くなった部位が何秒で元の色に戻るかを測定する簡便な循環評価法です。
正常では1~2秒以内で色が戻りますが、ショック状態では2秒以上かかることがあります。
さらに、ショックの原因に応じて追加の検査が行われます:
- 血液量減少性ショックが疑われる場合:胸腔や腹腔内への出血の有無を、X線や超音波検査などで確認
- 心原性ショックが疑われる場合:聴診、心電図検査、超音波検査(心エコー)を用いて、心拍リズムや心機能の評価を行います
これらの診断情報を組み合わせて、ショックの有無や重症度を総合的に判断し、原因に応じた治療方針を速やかに決定する必要があります。
ショックの治療
ショックが疑われた場合は、直ちに酸素供給と循環支持が必要です。
- 酸素吸入:全身の酸素不足を改善
- 輸液療法:血管内の血液量を増やし、心拍出量を上げる
- 強心薬や昇圧薬の使用:血圧が回復しない場合に使用
- アナフィラキシーショック:アドレナリンの投与が有効
- 心原性ショック:原因に応じた心機能のサポート(心電図・超音波などで評価)
症状のタイプに応じた迅速な治療が、命を救う鍵となります。
予後
ショックは生命を脅かす非常に危険な状態であり、対応が遅れれば臓器障害が進行し、短時間で死に至る可能性があります。
しかし、早期に原因を特定し、的確な治療を行えば回復できるケースもあります。
⚠️ 予後は、原因疾患の重症度、治療開始までの時間、全身状態によって大きく左右されます。
まとめ
犬の「ショック」は、日常的な驚きとはまったく異なる、重篤な医学的緊急事態です。
ぐったりしている、脈が弱い、呼吸が浅い――そんなときは迷わず動物病院を受診しましょう。
原因に応じた迅速な治療が、命を守るために何よりも重要です。
獣医師の説明をしっかり受け、わからない点は遠慮なく確認するようにしましょう。