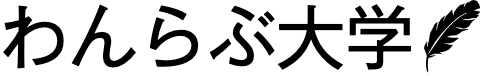この記事では、犬のネフローゼ症候群について原因、症状、診断そして治療を、現役獣医師が解説しています。
最後まで読むだけで、ネフローゼ症候群について誰にでもすぐに理解できるように作成しているので、是非一度目を通していただけると嬉しいです。
ネフローゼ症候群とは
ネフローゼ症候群は、腎臓にある糸球体の異常で、尿中にタンパクが多量に漏れる病気です。
腎臓は腰のあたりに左右に2個存在する臓器で、代表的な働きは体液のバランスを一定に保つため、血液をろ過して尿という形で老廃物や水分などを排泄することです。
腎腎臓は、「ネフロン」と呼ばれる特殊な構造が多数集まってできています。その「ネフロン」は、数本の毛細血管が球状に絡まった「糸球体」と、糸球体からつながる「尿細管」という管でできています。
糸球体は、血液をきれいにする濾過装置として働き、尿細管は、体に必要な成分や水分を再び吸収、不要な物質の分泌(排泄)をする働きがあります。
腎臓の糸球体が障害されると、尿中に血液中のタンパクであるアルブミンが多量に漏れるため、血液中のアルブミンが減り、低アルブミン血症(低タンパク血症)がみられます。そして低アルブミン血症が、浮腫(むくみ)を引き起こします。
ラブラドールレトリバーやゴールデンレトリバーでの発生が多いとされています。
原因
腎臓の組織構造は、糸球体と尿細管に大別されます。
病変が主に糸球体にある腎臓病を、糸球体疾患と言います。糸球体疾患の発生は中高齢の犬に多く発生し、犬の慢性腎臓病の50%以上に糸球体疾患が存在すると報告されています。
糸球体疾患の発生には、基礎疾患が関与すると考えられています。基礎疾患として、以下の病気が考えられます。
- 感染症や炎症
- 腫瘍
- 自己免疫疾患
- 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)
ネフローゼ症候群の症状
ネフローゼ症候群では、低アルブミン血症に伴う浮腫(むくみ)や腹水が代表的な症状です。
しかし、明らかな症状を示さないこともあれば、体重減少や食欲低下などの一般的な症状であることもあります。
その他に、腎不全、血栓塞栓症、高血圧やそれに伴う失明などがみれらることもあります。
ネフローゼ症候群の診断
タンパク尿、低タンパク血症、低アルブミン血症、高コレステロール血症そして浮腫の併発が、このネフローゼ症候群の特徴的な所見です。
そのため、まず血液検査と尿検査を行います。
血液検査では、低タンパク血症、低アルブミン血症、高コレステロール血症がみられます。


尿検査ではタンパク尿がみられ、尿タンパク/クレアチニン比(UPC)が高値を示します。
尿中タンパク/クレアチニン比(UPC)は、尿タンパク濃度をクレアチニン濃度で割ったものであり、尿の濃い薄いに関わらず尿に漏れたタンパク質が有意なものかどうかの判定に必要な検査です。
犬と猫では、UPCは0.2未満が正常であり、0.4以上では有意なタンパク尿だと考えられます。
検査結果で、①タンパク尿の原因が腎臓以外には考えられない、②尿検査で尿検査での尿蛋白/クレアチニン比(UPC)が持続的に高値を示す場合は、ネフローゼ症候群と一致します。
同時に、レントゲン検査や超音波検査などの画像検査を行い、基礎疾患の検査も併せて行います。基礎疾患がある場合には、その治療も必要となるからです。
可能であれば腎臓の生検を行い、病理組織学的検査を実施することが推奨されています。
糸球体疾患は「免疫複合体性糸球体腎炎」、「非免疫複合体性糸球体腎炎」、「腎アミロイド症」の3つに分類されますが、これは病理組織学的検査でのみ判断が可能だからです。
そしてこの分類は、治療法の選択と予後に関連します。
ネフローゼ症候群の治療
まず、基礎疾患の治療と糸球体疾患の治療が必要となります。
基礎疾患の治療は、その基礎疾患に応じた治療を行います。糸球体疾患は、グルココルチコイド(ステロイド)の使用で悪化する可能性が指摘されています。そのため、自己免疫疾患などで、治療にグルココルチコイド(ステロイド)が必要な場合には注意が必要です。
糸球体疾患の治療は、慢性腎臓病の治療に準じます。食事も同様に腎臓病用の療法食が推奨されています。

もし、基礎疾患の治療で必要な食事療法がある場合、優先順位の高い方を優先します。
同時に、タンパク尿に対する治療と低アルブミンに対する治療を行います。
タンパク尿に対する治療は、アンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬)の投薬です。また、高血圧の場合には、降圧剤(血圧を下げる薬)を併用を検討します。
低アルブミンになると、腹水や浮腫(むくみ)がみられ、さらに血栓塞栓症を発症しやすくなります。そのため、腹水や浮腫(むくみ)に対する治療として、利尿剤の投与を行い、血栓塞栓症の予防を目的として、抗血小板療法を行います。
免疫抑制療法
以下の場合に、免疫抑制療法を検討します。
- 病理組織学的検査で免疫複合体性糸球体腎炎と診断された場合
- 尿検査で尿蛋白/クレアチニン比(UPC)が3.0を超える重度の蛋白尿の場合
- 血液検査でアルブミン(ALB)が2.0mg/dlを下回る低蛋白血症がみられた場合
予後
予後は基礎疾患によりますが、一般にネフローゼ症候群を起こした糸球体疾患は予後が悪いとされています。
逆にネフローゼ症候群を起こす前ならば、基礎疾患の治療が良好であれば、タンパク尿が改善しなくても、長期間良好に経過することもあります。
まとめ
犬のネフローゼ症候群について解説しました。腎臓にある糸球体の異常で、尿中にタンパクが多量に漏れる病気で、それに伴い、腹水や浮腫、腎不全、血栓塞栓症、高血圧、失明などの症状がみられるようになってきます。
蛋白質(TP)の低下、アルブミン(Alb)の低下、総コレステロール(T-Cho)の上昇が見つかった場合にはこの病気を疑い、必ず尿検査を実施するようにしましょう。