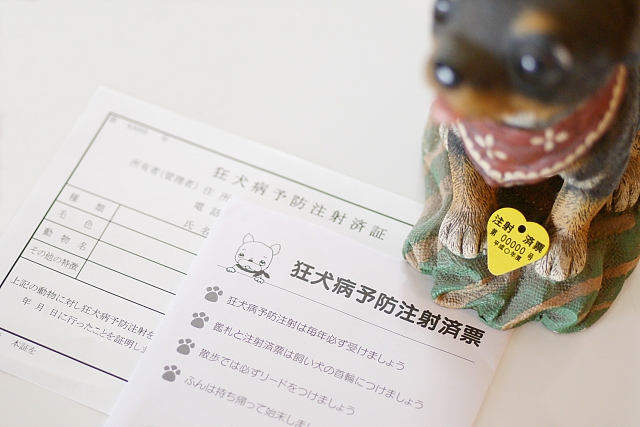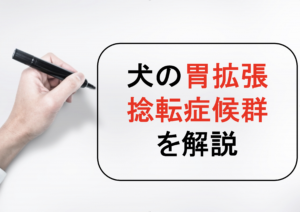犬の「混合ワクチン」は、命にかかわる感染症から愛犬を守る大切な予防注射ですが、法律で義務づけられている「狂犬病ワクチン」とは違い、混合ワクチンはあくまで飼い主の判断に委ねられた「任意接種」です。
そのため、「打つ」「打たない」という選択肢があり、どのように考えるべきか迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、混合ワクチンの種類や予防できる病気、副作用の可能性などを獣医師の立場から丁寧に解説します。「本当に打つべき?」という疑問にも向き合いながら、納得のいく判断ができるようお手伝いします。
この記事はこんな飼い主さんにおすすめです
・混合ワクチンって結局どういうもの?と疑問をお持ちの方
・愛犬に何種のワクチンを打てばいいのか迷っている方
・副作用が心配で接種をためらっている方
ワクチンとは?〜「模擬試験」で免疫をつける仕組み〜
病気にかかる前に、「この病原体は危ない!」と体にあらかじめ知らせておく――それがワクチンの役割です。感染症のなかには、軽い風邪のように自然に治るものもあれば、重症化して命に関わるものもあります。
こうした重い感染症に備えて、事前に免疫をつけておくことがとても重要です。
人の例でいえば、麻疹(はしか)・風疹・水痘(みずぼうそう)などが代表的なワクチン対象の病気です。これらは一度感染すると重い症状を引き起こすことがあり、予防がとても大切な感染症です。
ワクチンとは、ウイルスや細菌などの病原体を弱らせたり、感染力をなくしたりしたうえで体内に投与することで、あらかじめ免疫をつける医療技術です。実際に病気にかかる代わりに、「模擬試験」のような形で免疫の学習をさせる――そんなイメージがわかりやすいかもしれません。
一度ワクチンで覚えた病原体に対しては、体の免疫が「記憶」して再び入ってきても素早く反応し、病気を防いだり、重症化を防いだりする効果があります。
ワクチンの種類:生ワクチンと不活化ワクチン
ワクチンには、大きく分けて「生ワクチン」と「不活化ワクチン」の2種類があります。それぞれ特徴と注意点があるため、接種スケジュールを立てるうえでも知っておくことが大切です。
生ワクチン
病原体の毒性を弱めただけで殺してはいない状態のワクチンです。体内で一時的に増殖し、自然感染に近い形で免疫がつくられます。
✅ 長期間の免疫が得られやすい
⚠️ 副作用がやや出やすい(発熱、アレルギー反応など)
不活化ワクチン
病原体を完全に感染不能な状態にした(殺した)ワクチンです。体内では増殖しませんが、免疫システムは異物として認識し、抗体をつくります。
✅ 安全性が高く、副作用は比較的少ない
⚠️ 免疫の持続時間が短いため、追加接種が必要
ワクチン接種のタイミングと注意点
ワクチンを複数接種する場合、種類によって間隔に注意が必要です。
- 生ワクチン同士の接種:
→ 最低でも4週間(28日)以上の間隔を空ける必要があります。
(例:麻疹と風疹を別々に打つ場合) - 不活化ワクチン同士や、生ワクチンと不活化ワクチンの組み合わせ:
→ 接種の間隔は2週間程度で可能なこともありますが、具体的なワクチンの種類によって異なります。獣医師の指示を必ず確認しましょう。
犬の混合ワクチンとは
混合ワクチンとは、複数の感染症に対して一度の注射でまとめて免疫をつけられるように作られたワクチンです。
現在、国内の動物病院では主に5種から10種程度の混合ワクチンが使用されており、犬の健康状態や飼育環境、地域の感染症リスクなどに応じて選ばれます。
特に子犬は免疫力がまだ未熟なため、命にかかわるような重い感染症にかかりやすい時期です。中でも注意すべきは、致死率の高い犬ジステンパー、犬伝染性肝炎、犬パルボウイルス感染症などで、これらはいずれも重症化しやすく、治療が難しい感染症です。
そのため、混合ワクチンの接種は、子犬をこれらの深刻な感染症から守るための非常に重要な予防手段といえるでしょう。
なお、混合ワクチンの種類は年によって若干の変動があり、製造中止や新製品の発売によってラインナップが変更されることがあります。現在でも1種〜3種程度の単独または少数成分のワクチンも存在しますが、これらは主にブリーダーや繁殖現場で、初期免疫を目的に使用されます。
そのため、実際に愛犬が接種すべき混合ワクチンの種類は、飼育環境や地域性、犬種や体質を考慮しながら、かかりつけの動物病院で相談のうえ決定することが大切です。
混合ワクチンの種類ごとの構成内容
混合ワクチンは、カバーする病気の数によって「○種ワクチン」と呼ばれ、種類が増えるごとにより多くの病気に対応できます。
3種ワクチン
以下の基本的なコアワクチン3種をカバーします。
- 犬ジステンパー
- 犬パルボウイルス感染症
- 犬伝染性肝炎(アデノウイルス1型)
5種ワクチン
上記3種に加えて、以下の呼吸器系のウイルス感染症2種が加わります。
- 犬アデノウイルス2型感染症
- 犬パラインフルエンザウイルス感染症
※この5種が現在の標準的なベース構成とされ、ほとんどの混合ワクチンに含まれています。
6種ワクチン
5種に加えて、以下の病気が追加されます。
- 犬コロナウイルス感染症(消化器症状)
7種ワクチン
5種に加えて、人獣共通感染症であるレプトスピラ感染症のうち、以下の2型をカバーします。
- レプトスピラ(コペンハーゲニー型)
- レプトスピラ(カニコーラ型)
8種ワクチン
6種に加えて、さらに以下のレプトスピラ型が追加されます。
- レプトスピラ(コペンハーゲニー型)
- レプトスピラ(カニコーラ型)
9種ワクチン
7種に加えて、さらに以下のレプトスピラ型が追加されます。
- レプトスピラ(ヘブドマディス型)
- レプトスピラ(オータムナリス型)
10種ワクチン
8種に加えて、さらに以下のレプトスピラ型が追加されます。
- レプトスピラ(ヘブドマディス型)
- レプトスピラ(オータムナリス型)
11種ワクチン
10種に加えて、さらに以下のレプトスピラ型が追加されます。
- レプトスピラ(オーストラリス型)
混合ワクチンで予防できる病気とは?
混合ワクチンで予防できる感染症には、命にかかわる重篤なものから、他のウイルスとの混合感染で悪化しやすいものまでさまざまな種類があります。
特に子犬で致死率が高く、すべての犬に対して接種が推奨されている「コアワクチン」として重要なのが、犬ジステンパー、犬伝染性肝炎(アデノウイルス1型)、犬パルボウイルス感染症です。
犬ジステンパー
高熱、目やに、鼻水が出て、元気や食欲がなくなり、嘔吐や下痢、咳、さらにはけいれんなどの神経症状が現れます。
特に神経症状が出ると死亡率が高く、助かっても麻痺などの後遺症が残ることがあります。
ペットショップやブリーダーで子犬の集団発生が報告されることもあり、3〜6か月齢の若い犬がもっとも発症しやすいといわれています。

犬パルボウイルス感染症
主に経口感染でうつり、激しい嘔吐・下痢を繰り返し、食欲もなくなり、急速に衰弱していきます。
重症になると短時間で脱水症状が進み、死亡することもある非常に恐ろしい感染症です。
生後4〜12週齢の「移行抗体」が減少する時期に感染リスクが高く、とくに生後4か月齢までは要注意です。

犬伝染性肝炎(アデノウイルス1型感染症)
発熱、腹痛、嘔吐、下痢が見られ、進行すると目が白く濁る(角膜混濁)こともあります。
また、子犬では症状が出ないまま突然死することもあり、油断できない感染症のひとつです。
これら3つの疾患はいずれも致死率が高く、治療が難しい感染症です。混合ワクチンの最も基本的な構成に含まれており、すべての犬に対して接種が強く推奨されます。
その他、混合ワクチンで予防できる感染症
以下の感染症も、ワクチンの種類によって予防することが可能です。接種するワクチンの構成によって、どこまで予防範囲を広げるかが変わってきます。
- 犬アデノウイルス2型感染症:咳、鼻水、発熱などの呼吸器症状が中心で、肺炎を起こすこともあります。
- 犬パラインフルエンザウイルス感染症:咳やくしゃみといった風邪のような症状を示し、他のウイルスとの混合感染や細菌による二次感染で重症化することがあります。
- 犬コロナウイルス感染症:嘔吐や水様性下痢などの消化器症状を引き起こします。成犬では軽症で済むことが多い一方、子犬では重症化することもあるため注意が必要です。
- 犬レプトスピラ感染症(人獣共通感染症):発熱、黄疸、出血傾向などがみられ、人にも感染する危険性がある細菌感染症です。複数の血清型(2〜5型)に分かれ、製品によって対応できる型が異なります。
※レプトスピラワクチンの接種判断については、副反応リスクや地域性も考慮が必要です。詳細は「何種の混合ワクチンを接種するべきか?」のセクションをご覧ください。
何種の混合ワクチンを接種するべきか
混合ワクチンの種類は、レプトスピラ症を予防するかどうかによって大きく変わってきます。
犬ジステンパーやパルボなどの「コアワクチン」はすべての犬に必要ですが、レプトスピラ症に関しては、その必要性が飼育環境や地域の感染リスクによって異なります。
日本では、都市部ではレプトスピラ症の発生が少なく、地方や水辺の多い地域では比較的多いとされています。そのため、まずはお住まいの地域の感染状況を考慮することが第一のポイントです。
「それなら、念のため全国すべての犬にレプトスピラ入りのワクチンを接種すべきでは?」と考える方もいるかもしれませんが、実はそれほど単純な話ではありません。
レプトスピラワクチンには、2〜5型の血清型(カニコーラ型、コペンハーゲニー型など)を含むものがありますが、他のワクチン成分と比較して副反応が出やすい傾向があるとされています。
実際に日本で行われた研究(Miyaji K, et al., 2012. Vet Immunol Immunopathol 145:447–452)でも、レプトスピラワクチンを含む混合ワクチンでは、アレルギー反応やアナフィラキシーの発生率が高いことが報告されています。
特に、小型犬やアレルギー体質の犬、なかでもミニチュアダックスのような犬種では副反応のリスクが高いとされており、慎重な判断が求められます。
そのため、
- お住まいの地域でレプトスピラ症の発生があるか
- 犬種や体質的にアレルギー反応を起こしやすいか
- 過去にワクチン接種で副反応を経験したことがあるか
といった要素を総合的に評価したうえで、獣医師とよく相談しながら、レプトスピラを含むかどうかを決めていくことが大切です。
なお、過去にレプトスピラを含む混合ワクチンでアレルギー反応が出た場合には、次回からはレプトスピラを除いた構成のワクチンに変更するという対応も選択肢のひとつです。
混合ワクチン接種のタイミング
犬の混合ワクチンは、「子犬の初年度ワクチン」と「成犬になってからの追加接種」で考え方が大きく異なります。それぞれのステージに合わせて、適切な接種スケジュールを立てることが大切です。
子犬の場合(初年度ワクチン)
子犬は、生まれた直後に母犬からもらう「移行抗体」によって感染症から守られています。しかし、この移行抗体は徐々に減っていく一方で、残っているとワクチンの効果を打ち消してしまうことがあります。
そのため、どのタイミングでワクチンを接種するかは、個体差があるもののとても重要です。
世界小動物獣医師学会(WSAVA)のワクチネーション・ガイドライン(2015年)では、以下のように推奨されています:
6〜8週齢からワクチン接種を開始し、2〜4週間隔で追加接種を繰り返し、最終接種は16週齢またはそれ以降に行う
一方、日本国内のワクチン添付文書に関する調査(「犬用ワクチンの概説」日本獣医学会誌, 2010年)では、以下のように記載されています:
- 初回接種は4週齢〜12週齢未満までと幅があり
- 接種回数は1〜3回(多くは2回)
- 接種間隔は3〜4週間が一般的
- 妊娠中の犬には使用を避けるといった制限もある
このように、ワクチンの種類やメーカーによって添付文書の記載に違いがあり、国内で統一されたスケジュールは存在していないのが実情です。
そのため、国際的に最も信頼性が高いとされるWSAVAガイドラインを参考にして、動物病院で適切なタイミングを見極めながら接種していくことが推奨されます。
成犬の場合(追加接種)
日本では現在、年1回の混合ワクチン接種が一般的に行われています。
しかし近年では、「ワクチンの免疫はもっと長く持続するのではないか?」という議論があり、コアワクチンは3年ごとの接種でも十分ではないかという考え方も広がりつつあります。
WSAVAガイドラインでも、次のように記載されています:
- コアワクチン(ジステンパー・パルボ・アデノ1型)
→ 初年度接種後は、原則3年以上の間隔をあけるべき - ノンコアワクチン(アデノ2型、パラインフルエンザ、コロナ、レプトスピラなど)
→ 免疫持続期間が短いため、毎年接種が望ましい
ただし現実には、トリミングサロンやペットホテルなどで「ワクチン接種から1年以内の証明書」が求められることが多いため、たとえコアワクチンだけであっても、3年ごとの接種がすぐに普及するのは難しいのが現状です。
混合ワクチンの抗体検査という選択肢も
「追加接種が本当に必要かどうか」を確認する手段として、抗体価検査を行うこともできます。
この検査では、以下の3つのコアワクチンに対する血中の抗体量を測定します:
- 犬ジステンパーウイルス
- 犬パルボウイルス2型
- 犬伝染性肝炎(アデノウイルス1型)
この検査結果によって、十分な免疫が残っていると判断された場合には、その年の混合ワクチンを見送ることが可能です。
🧪 抗体検査は「免疫が残っているかどうか」を可視化できる有用な手段です。年1回の追加接種が負担になっている場合や、副作用が心配な飼い主さんは、一度検討してみるのもよいでしょう。
このように、ワクチンの接種タイミングは「一律」ではなく、犬の年齢・生活環境・健康状態に合わせて柔軟に考えていくことが大切です。獣医師と相談のうえ、愛犬にとって最も安心できる予防計画を立てましょう。
混合ワクチン接種後の注意事項
ワクチンを接種した当日から2〜3日ほどは、激しい運動やシャンプーを避け、安静に過ごすことが大切です。
とはいえ、軽めのお散歩程度であれば、当日でも問題はありません。運動の内容に注意しながら、無理のない範囲で過ごさせてあげましょう。
また、ワクチンによって免疫がしっかりつくまでには通常2〜3週間かかるといわれています。
その間は、ドッグランや多頭飼育の犬との接触はなるべく控え、感染リスクの高い場所には連れて行かないようにしましょう。
そしてもう一つ大事なのが、接種後の体調観察です。
アレルギー反応や副作用が起こる場合もあるため、接種後しばらくは愛犬の様子をよく観察し、異常がないか注意深く見守るようにしてください。
混合ワクチン接種後に起こりうる副作用
ワクチン接種後には、ごくまれに次のような副反応がみられることがあります:
- 顔面の腫れ(いわゆる「ムーンフェイス」)
- かゆみ、蕁麻疹などの皮膚症状
- 元気消失、ふらつき、ぐったりする(ショック症状)
- 血圧や体温の低下、可視粘膜の蒼白
- 呼吸困難や意識障害などのアナフィラキシーショック
これらの反応は接種後30分以内に現れることが多く、重度の場合は命に関わる可能性もあるため要注意です。
日本で行われた研究(Miyaji K, et al., 2012. Vet Immunol Immunopathol 145:447–452)によると、
- 顔面浮腫などの皮膚症状は10,000頭あたり42.6頭
- 虚脱やアナフィラキシー様反応は10,000頭あたり7.2頭
という報告があります。発生頻度は高くはありませんが、決してゼロではないことを理解しておくことが大切です。
安全に接種を行うために
アレルギーやアナフィラキシーのリスクに備える意味でも、ワクチンはなるべく午前中に接種することをおすすめします。
何か異変があった場合でも、すぐに動物病院を受診できる時間帯の方が安心です。
接種後は、無理のない範囲で安静に過ごさせ、愛犬の体調や様子にしっかりと目を配ってあげることが、何よりのケアになります。
混合ワクチン接種後、2〜3日の間は激しい運動やシャンプーを等を避けて安静にする必要があります。そのため、激しい運動をさせない軽いお散歩程度であれば、混合ワクチン接種当日でも問題ないです。
またワクチン接種後、免疫が得られるまで2〜3週間かかるので、それまでは犬同士の接触を避ける必要があります。すぐにはワクチンの効果が得られない点に、注意をしましょう。
さらに副作用が出てないか、帰宅してからもよく観察をしましょう。
混合ワクチン接種後の副作用
顔面浮腫(ムーンフェイス)、掻痒、蕁麻疹などのアレルギー反応やショック症状(血圧、体温の低下、可視粘膜蒼白など)、意識障害そして呼吸困難などのアナフィラキシーショックに注意する必要があります。
日本で行われた、犬におけるワクチン接種後の副反応について調べた調査では、顔面浮腫などの皮膚症状が10,000頭あたり42.6頭、虚脱などのアナフィラキシーが10,000頭あたり7.2頭と報告(Miyaji K, et al., 2012. Vet Immunol Imunopathol 145:447-452)されています。
可能であれば、アレルギー症状やアネフィラキシーショックなどの副反応が出ても動物病院にすぐに連れて行けるように、混合ワクチンは午前中に接種することをお薦めします。混合ワクチン接種後は安静にして、ゆっくりと愛犬の様子を見てあげましょう。
まとめ
今回は、犬の混合ワクチンについて詳しく解説しました。
混合ワクチンには複数の種類があり、接種のタイミングや内容は、犬の年齢や体質、生活環境によって異なります。どのワクチンを、どのような間隔で接種すべきかは、かかりつけの獣医師と相談しながら、愛犬にとって最適なプランを立てることが大切です。
また、ワクチン接種後にはまれに副作用が現れることがあります。アレルギー反応やアナフィラキシーなど、万が一の事態にすぐ対応できるように、なるべく午前中に接種を行い、その後は体調の変化に注意しながら安静に過ごすようにしましょう。
大切な家族である愛犬の健康を守るために、正しい知識と適切な予防を心がけていきましょう。