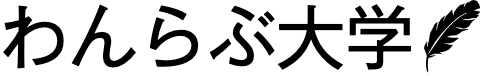この記事では、犬のパルボウィルス感染症について原因、症状、診断そして治療を、現役獣医師が解説しています。
最後まで読むだけで、パルボウィルス感染症について誰にでもすぐに理解できるように作成しているので、是非一度目を通していただけると嬉しいです。
犬パルボウイルス感染症とは
犬のパルボウイルス感染症は、犬パルボウイルスの感染によって起こる病気です。特に子犬では、重度の胃腸症状を起こし死亡する場合もあります。
パルボウイルスは、エンベロープを持たない直鎖一本鎖DNAウイルスです。特定の種間で感染し、細胞分裂が盛んな腸管、骨髄そしてリンパ系組織に感染します。
パルボウイルス感染症は100年以上も前に、猫汎白血球減少症(猫パルボウイルス)が発見されました。
その後に、犬のパルボウイルス(犬パルボウイルス1型)が、胃腸および呼吸器症状を示す犬の原因ウィルスとして発見されました。
さらに、重度の胃腸症状を呈し高い死亡率を引き起こす、パルボウイルス(犬パルボウイルス2型)が発見されました。
犬のパルボウイルスは、犬パルボウイルス1型とパルボウイルス2型が存在します。
- 犬パルボウイルス1型:通常無症状
- 犬パルボウイルス2型:重度の胃腸症状がみられる
犬パルボウイルスの感染は、離乳期後の生後4~12週齢の移行抗体が低下する頃に、感染のピークを迎えます。その後、4ヶ月齢までは感染がしばしばみられます。
原因
犬パルボウイルス感染症は、糞便や吐物内のパルボウイルスを口や鼻から摂取することで感染します。
パルボウイルス感染症の犬からの糞便へのウイルスの排出は、症状が出るよりも早く、感染後4~5日目から始まります。このウイルスの排出期間は、7~10日間です。そのためウイルスの排出は、通常感染から14日目までには終わるとされています。
犬パルボウイルス感染症の症状
犬パルボウイルス感染症は、子犬と成犬で症状が異なります。
子犬の場合
急性の嘔吐、下痢、元気消失、発熱が典型的な症状です。その結果として、脱水症状を生じます。
潜伏期間は感染後3~7日です。そして、その後に症状がみられます。
子犬においては、臨床症状の発現後24時間以内に死亡するケースもあります。
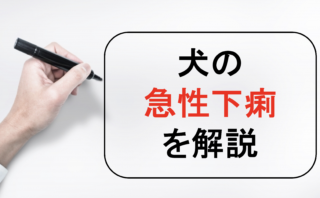
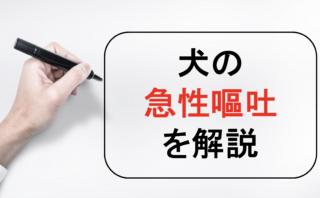
成犬の場合
無症状であることが多いです。症状があったとしても、子犬ほど激しい症状を示す場合は少ないです。
犬パルボウイルス感染症の診断
子犬に急性の嘔吐、下痢、元気消失、発熱などの症状がみられた場合に、犬パルボウイルスを疑います。
パルボウイルス抗原検査キットが診断に有用です。この抗原は、感染して4~7日目に検出のピークを迎えるとされています。
犬パルボウイルスを検出するPCR検査も存在します。PCR検査は、抗原検査キットよりも感度が高いです。しかし、検査結果が出るまでに時間がかかるデメリットがあります。
PCR検査は、以下の理由で検査のタイミングが重要となります。
- パルボウイルスの生ワクチンを接種した後、4~10日は偽陽性を示すことがある
- パルボウイルス感染後、10~12日目以降はウイルスの排出量が減少するため、陰性となる可能性がある
血液検査では、白血球数の減少(白血球数:500〜2000/μℓ程度)がみられます。これは、好中球の減少と同時に、リンパ球の減少もみられるためです。
犬パルボウイルス感染症の治療
犬パルボウイルス感染症の治療は、以下の対症療法が中心となります。
- 低血糖の改善
- 脱水の改善
- 電解質異常に対する輸液療法
- 抗菌薬の投与
- 制吐剤の投与
- 経腸栄養剤
- コロイド輸液
栄養や水分などを点滴することによって補充する治療
ほとんどの場合は嘔吐を伴うので、投薬が困難なので、入院による点滴治療が必要なことが多いです。
パルボウイルスの消毒
犬パルボウイルス1型そして2型は、極めて抵抗性の強いウイルスです。自然環境下で7ヶ月以上も生存します。そして、ほとんどの消毒薬に抵抗性を示すことが知られています。
消毒は、32倍に希釈した漂白剤および四級アンモニア系消毒薬が有効であると報告されています。
予後
犬パルボウイルス感染症は、治療の有無で生存率が異なることが知られています。
- 無治療の場合:生存率は9.1%
- 積極的に治療を行った場合:生存率は80~95%
なお、入院治療で腸炎から回復した(約3週間)犬の糞では、ウイルスの感染力はほとんどないとされています。
予防
犬パルボウイルス感染症は、混合ワクチンに必ずコアワクチンとして含まれているので、予防が可能です。
まとめ
犬のパルボウイルス感染症について解説しました。この病気は無治療の場合の生存率は9.1%ですが、積極的に治療を行った場合の生存率は80~95%と、治療の効果が期待できます。
この病気の厄介な点として、犬パルボウイルス1型そして2型は、極めて抵抗性の強いウイルスだという事です。そのため、同居犬などへの感染にも留意しなければなりません。