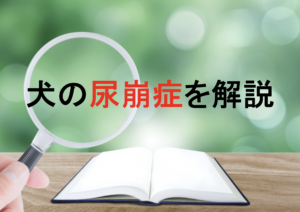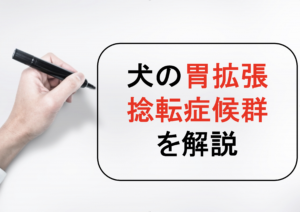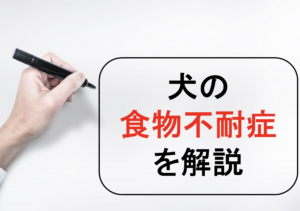この記事では、犬のガストリノーマについて原因、症状、診断そして治療を、現役獣医師が解説しています。
最後まで読むだけで、ガストリノーマについて誰にでもすぐに理解できるように作成しているので、是非一度目を通していただけると嬉しいです。
ガストリノーマとは
ガストリノーマは、ガストリンというホルモンを過剰に分泌する腫瘍で、胃酸の分泌過剰に関連した症状を起こす病気です。
胃のG細胞などから分泌されるホルモン。①胃主細胞からのペプシノゲン分泌促進作用、②胃壁細胞からの胃酸分泌促進作用、③胃壁細胞増殖作用、④インスリン分泌促進作用などの働きがあります。
ガストリノーマは、主に膵臓や十二指腸でみられる腫瘍です。ガストリノーマは、胃酸が過剰分泌されることにより胃潰瘍や十二指腸潰瘍などがみられます。別名、ゾリンジャー・エリソン症候群と呼ばれます。
膵臓は胃の後ろにある臓器で、代表的な働きは①膵液という消化液を分泌し、その中の消化酵素で食べ物の消化を助ける、②インスリンなどのホルモンを分泌し、血糖値を一定濃度にコントロールすることです。
膵臓の内部に、ランゲルハンス島という内分泌を行う細胞があります。ランゲルハンス島の細胞はいくつかに分類され、それぞれからホルモンが分泌されます。
- α細胞:グルカゴン
- β細胞:インスリン
- δ細胞:ソマトスタチン
膵臓に発生する腫瘍として、インスリノーマやグルカゴノーマが有名です。


ガストリノーマの発症の平均年齢は、8.2歳とされています。雌に発生する危険性がわずかに高いようです。好発犬種は知られていません。
原因
ガストリノーマ発生の明確な理由は、分かっていません。
ガストリノーマの症状
ガストリノーマでは、慢性嘔吐、元気や食欲の低下、体重減少、吐血、血便(黒色便)、粘膜蒼白、そして腹痛などの消化器症状がみられます。

これは、ガストリンの過剰分泌により胃酸が過剰分泌され、胃粘膜の肥厚、消化管潰瘍、食道炎などが起こった結果みられる症状です。
さらに症状が進行すると、消化管穿孔を引き起こすことがあります。この場合には、容体が急激に悪化し、ぐったりしてショックがみられます。

似たような症状を起こす病気として、以下の病気があります。
- 難治性の胃炎や胃潰瘍
- 炎症性腸疾患(IBD)
- 消化管の腫瘍
- 膵炎
ガストリノーマの診断
ガストリノーマは、診断が困難な腫瘍のひとつです。血液検査、レントゲンや超音波検査などの画像検査、内視鏡検査などを行い、総合的に判断していきます。
ヒトのガストリノーマでは、血清ガストリンの基礎濃度やセクレチン刺激試験を行いますが、犬や猫でこれらの検査は確立されていません。
膵臓腫瘍は、非常に見つけにくい腫瘍です。そのため、以下の場合にはガストリノーマの確率は極めて低いです。
- 触診でお腹の中に”できもの”が触れる場合
- 超音波検査で確認できた場合
- 開腹時に肉眼で見ることができる”できもの”があった場合
血液検査
血液検査では、以下の変化がみられます。
- 消化管出血による変化
貧血(再生性貧血)
低タンパク・低アルブミン血症 - 慢性嘔吐による変化
低カリウム血症
低ナトリウム血症
低クロール血症
画像検査
超音波検査では、肥厚した胃壁や幽門が観察される場合があります。
レントゲン検査では、消化管穿孔を起こしている場合、腹部の細部の構造が確認できなくなります。転移があれば、その所見がみられます。
内視鏡検査
内視鏡検査では、食道炎、胃または十二指腸潰瘍、胃粘膜の肥厚が確認されます。しかしこれらは、慢性の胃酸過多であることを示しているものの、ガストリノーマの証明にはなりません。
ガストリノーマの治療
ガストリノーマの治療は、対象療法と外科手術です。
対症療法は、胃酸の過剰分泌に関連する臨床症状を抑えるために、以下の治療を行います。
表面化している症状を緩和させ、苦痛を和らげるための治療
- H2受容体拮抗薬の投与
- プロトンポンプ阻害薬の投与
併せて、嘔吐に関連する電解質異常の補正を目的に輸液療法を行います。
可能であれば外科手術で、ガストリノーマと転移病巣の切除を行います。
予後
ガストリノーマは、転移率が高いため予後不良とされています。
内科的および外科的に治療した場合の生存期間は、平均4.8ヶ月と報告されています。
まとめ
犬のガストリノーマについて解説しました。この病気は診断が難しく、その上根治を目指す治療も難しい病気です。
今後、早期発見が可能な診断方法が開発されることが期待されます。