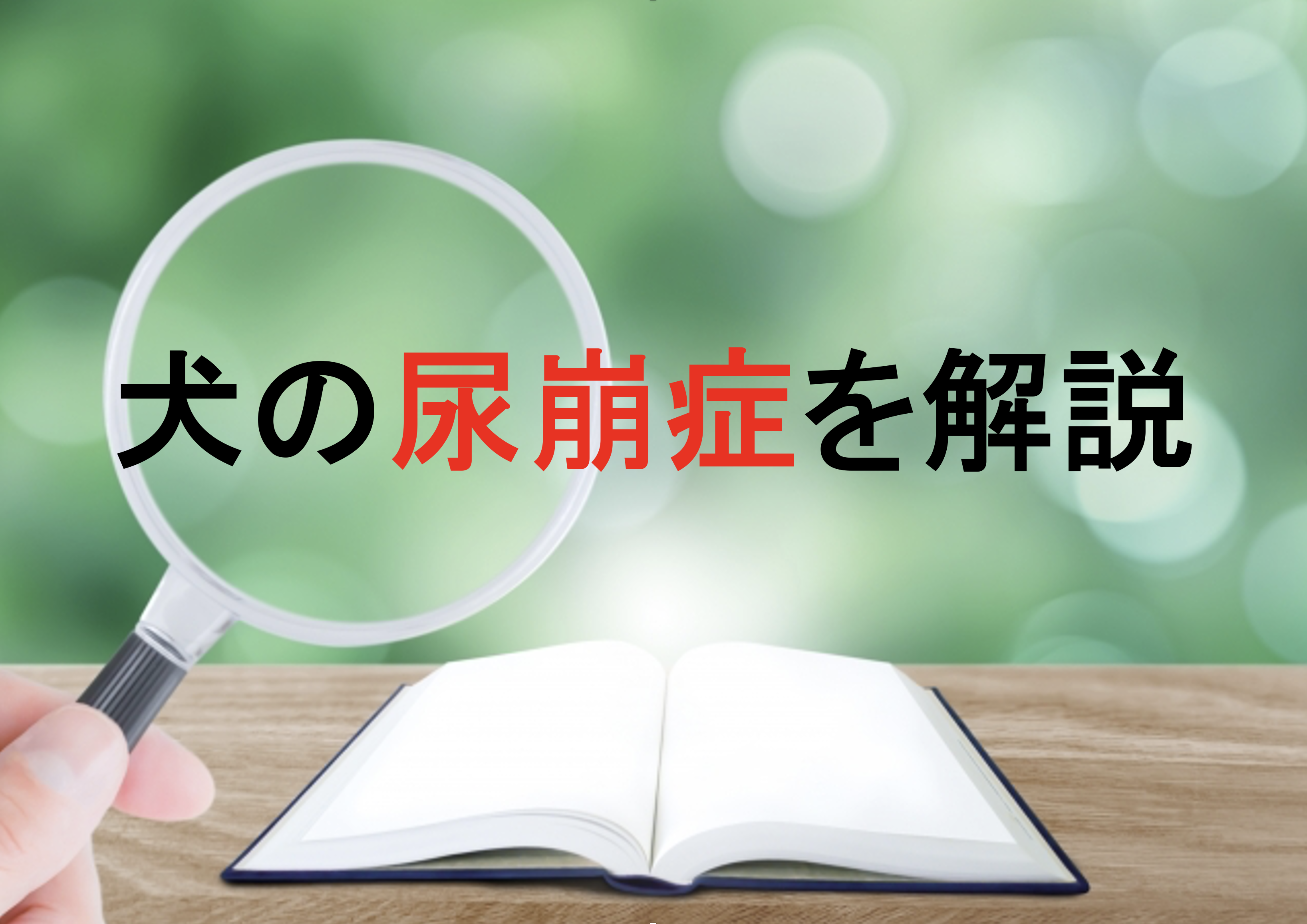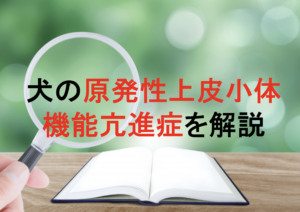この記事では、犬の尿崩症について原因、症状、診断そして治療を、現役獣医師が解説しています。
最後まで読むだけで、副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)について誰にでもすぐに理解できるように作成しているので、是非一度目を通していただけると嬉しいです。
尿崩症とは
尿崩症とは、腎臓でできた尿を十分に濃縮することができず、希釈された多量の尿が出る病気です。
腎臓は腰のあたりに左右に2個存在する臓器で、代表的な働きは体液のバランスを一定に保つため、血液をろ過して尿という形で老廃物や水分などを排泄することです。
この病気を理解するためには、腎臓での尿生成の過程を理解する必要があります。
腎臓に入った血液は糸球体で濾過され、尿の元となる原尿となります。この原尿は、ヒトではおよそ1日に150-180L生成されます。
次いで、原尿は尿細管で再吸収と分泌を受けて、最終的には約1%程度(ヒトでは1.5-1.8L)まで濃縮され、尿となり体外に排出されます。残りの99%は、再吸収され血液に戻ります。
そのため、水を再吸収が低下することで、尿を十分に濃縮することがでなくなると、希釈された多量の尿が出るようになります。
また、腎臓に関連するホルモンとして、アルドステロンとバソプレッシン(抗利尿ホルモン)があります。
アルドステロンは、副腎皮質から分泌されるホルモンで、腎臓でのナトリウムの再吸収を促進する働きがあります。
バソプレッシン(抗利尿ホルモン)は、脳の視床下部で合成され、脳下垂体後葉から分泌されるホルモンで、腎臓での水の再吸収を増加させる働きと、血管を収縮させて血圧をあげる働きがあります。
このように、尿崩症はバソプレッシン(抗利尿ホルモン)の合成または作用が低下することが原因で、水の再吸収が低下することで、尿を十分に濃縮することができず、多量の尿が出る病気です。
原因
尿崩症は、下垂体から分泌されるバソプレッシンの分泌障害に起因する「中枢性尿崩症」と、腎尿細管のバソプレッシンに対する受容体の反応性低下に起因する「腎性尿崩症」に大別されます。
尿崩症の最も多い原因は、種々の腎疾患によってバソプレッシンの反応性が低下することによって起こる「続発性尿崩症」です。
中枢性尿崩症
先天性
脳の視床下部や下垂体後葉の先天的な異常
後天性
下垂体腫瘍やそれに対する治療(放射線治療や摘出術)
外傷
腎性尿崩症
先天性
家族性の腎性尿崩症
後天性
種々の腎疾患に続発
尿崩症の症状
尿崩症の症状は、水をよく飲んでおしっこをたくさんする多飲多尿です。症状に関して、中枢性尿崩症と腎性尿崩症に違いはありません。
多飲多尿を起こす病気として、以下の病気も注意する必要があります。
尿崩症
慢性腎臓病
腎盂腎炎
腎性糖尿(ファンコーニ症候群)
副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)
副腎皮質機能低下症(アジソン病)
子宮蓄膿症
糖尿病
先端巨大症
甲状腺機能亢進症
抗利尿薬ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)
肝不全
多血症
薬剤(利尿薬、グルココルチコイド、フェノバルビタール)の投与
高カルシウム血症
ビタミンD中毒
原発性(心因性)多飲
尿崩症の診断
尿崩症の診断は、まず正確な飲水量を把握し、その後に尿検査を実施します。
尿崩症は、ほとんど場合多飲多尿を主訴として来院します。そのため、まず最初に行うことは、正確な飲水量を把握することです。
犬が1日に100ml/kg以上飲水しているようであれば、明らかに多飲と言えます。
例えば、5kgの犬であれば1日で500ml以上、10kgの犬であれば1日1,000ml以上の飲水量であれば、明らかな多飲と言えます。
次に、尿検査を複数回実施し、尿比重が1.008~1.015もしくはそれ以下の低張尿であることを確認します。
最終的には、前述の多飲多尿を引き起こす病気との鑑別が重要となります。
そのために、血液検査が必須となります。
血液検査で腎不全などの他の病気が否定され、尿比重が常に<1.006であれば、尿崩症が強く疑われます。
その場合には、水制限試験を実施し、バソプレッシンに対する反応を評価します。水制限試験を実施する際は、腎不全があると状態が悪化するリスクがあるため注意が必要です。
水制限試験とは、その名の通り犬の飲水を制限する試験です。これによって、中枢性尿崩症、腎性尿崩症、原発性(心因性)多飲を区別することができます。
尿崩症の治療
尿崩症の治療は、もし多尿が問題にならない環境であれば、自由に水分を摂取できるようにすることで十分です。
短期間の水分摂取不足でも、高ナトリウム血症や高張性脱水による神経症状などの致命的な症状が起こる可能性があります。
そのため、常に水を飲めるようにすることが重要です。
中枢性尿崩症の治療で、デスモプレシン点鼻薬を用いることがあります。しかし、腎性尿崩症の場合にはこの治療は無効です。

部分的な中枢性尿崩症や腎性尿崩症の場合に、サイアザイド系の利尿剤を用いる場合もあるようですが、効果は様々なようです。
予後
水が摂取できないと致死的となることがあるので注意が必要です。
まとめ
犬の尿崩症について解説しました。多飲多尿を起こす病気は、血液検査で原因が判明することが多いですが、この病気は最終的に水制限試験を行います。
尿崩症では、水分が摂取できないことで致命的な状況になるので、常に水を飲めるようにすることが重要です。