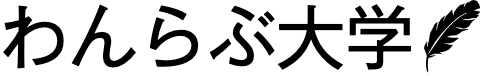愛犬に、紫色のアザが皮膚に見られる、歯茎や口腔粘膜からの出血、鼻出血、黒い便が出る(消化管出血)、紅茶のような尿が出る(尿路出血)といった症状が見られたら、どんな病気を考えますか?
出血し易くなり、血が止まりにくくなる「出血傾向」を示す病気の一つである、犬の免疫介在性血小板減少症について解説します。
免疫介在性血小板減少症とは
血小板とは血液に含まれる細胞で、骨髄中の巨核球の細胞質から産生されます。主に、血管壁が損傷した時に集合してその傷口をふさぎ、止血する役割を持ちます。
出血などで血管内皮細胞が傷害を受けると、血小板が血管内皮に接着し、血小板どうしが凝集し傷口を塞いで血栓を形成します。これを一次止血と呼びます。
その後、ここから凝固因子が放出されることによって、血液中にあるフィブリンが凝固し、さらに血小板や赤血球が捕らわれて、強固な止血栓が完成します。これを二次止血と呼びます。そして、これらが乾燥したものを一般に、「かさぶた」と呼びます。
血管壁が損傷した時に集合してその傷口をふさぎ止血する
免疫というのは、細菌やウイルスなどの異物を認識し排除するための役割を持ちますが、自分自身の正常な細胞や組織に対してまで過剰に反応し攻撃を加えてしまうことを自己免疫疾患と呼びます。犬の免疫介在性血小板減少症は、自分の血小板を異物であると認識して攻撃してしまう自己免疫疾患で、その結果として血小板減少症が起こる病気です。
自分の血小板を異物であると認識し、攻撃することで血小板減少症が起こる病気
原因
免疫介在性血小板減少症では、抗体が血小板表面に結合した結果、マクロファージ系細胞によって貪食されてしまいます。骨髄での血小板産生能は保持されているため、血小板の貪食による除去が血小板産生を上回った時に、血液中の血小板の減少が始まります。また抗体は、血小板細胞膜の構成要素に対するものと考えられており、抗体の結合により血小板の機能が低下することも報告されています。
血小板に対する抗体の産生
免疫介在性血小板減少症は、基礎疾患の関与しない「原発性」免疫介在性血小板減少症と、薬剤、ワクチン、腫瘍、感染症などの基礎疾患に続発する「二次性」免疫介在性血小板減少症に大別され、 原発性免疫介在性血小板減少症の発生が多いとされています。
免疫介在性血小板減少症の症状
血小板数が低値を示すことを、血小板減少症と呼びます。血小板が2.0×10⁴/μl未満になると、血液凝固異常により出血傾向が起こるとされています。
出血傾向とは、血小板の低下時に出血が抑制できない状態であり、皮膚の中での出血を示す「紫斑(紫色のアザ)」がみられることがあります。
出血し易くなり、血が止まりにくくなる。「紫斑」が代表的。
また、皮膚以外にも歯茎や口腔粘膜からの出血、鼻出血、黒い便が出る(消化管出血)、紅茶のような尿が出る(尿路出血)、重症の場合には脳出血などの症状が出ることがあります。
免疫介在性血小板減少症の診断と治療
診断
まず、血小板減少症が「偽血小板減少症」ではなく、真の血小板減少症であること確認する必要があります。「偽血小板減少症」とは、採血の不手際、抗凝固剤による血小板の凝集、アーチファクトによる希釈、血球計算機の限界(機械が正確に測定できない)といった理由で、実は血小板数が正常な状態のことです。
実際に血小板減少症があることが確認できたら、それが①産生低下、②消費/破壊亢進、③分布の異常、④喪失のうち、何が原因で起きているのかを検討します。
関連記事:犬の血小板の異常(血小板増加症/減少症)
免疫介在性血小板減少症の診断は、除外診断に基づきます。
血小板減少症をきたす他の疾患が無いか、血液検査、レントゲンや超音波などの画像検査、尿検査、糞便検査などで検討します。
また必要に応じて、骨髄検査や血液凝固線溶系検査(FDP(フィブリン分解産物)、PT(プロトロンビン時間)、APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)、AT(アンチトロンビン)、フィブリノーゲン)を行います。
実際に血小板減少症があることを確認して、他の血小板減少症をきたす疾患を除外する
治療
重症の症例では、入院して治療をすることが多いです。その理由として、この病気の死亡率は約30%と報告されており、その多くは初期経過中に死亡しているからです。
顕著な出血(特に消化管出血)により貧血が認められる場合には、輸血が必要になることがあるります。
初期治療は、グルココルチコイド(ステロイド)による免疫抑制療法が第一選択となります。また、免疫抑制剤を併用したり、ヒト免疫グロブリン製剤の投与なども行われます。
血小板数が基準範囲内まで増加した時点で、グルココルチコイド(ステロイド)の投与量の減量を考慮していきます。維持療法は軽症例で3ヶ月以上、重症例で6ヶ月以上程度継続していくことが推奨されています。
また、この病気は再発する可能性もありますので、投薬中止後にも定期的に検診を受けるようにしましょう。
予後
死亡率は約30%と報告されており、その多くは初期経過中に死亡することが多いです。
まとめ
犬の免疫介在性血小板減少症について解説しました。この病気は、死亡率は約30%と報告されており、その多くは初期経過中に死亡することが多いとされていますので、初期治療が重要になってきます。
紫色のアザが皮膚に見られる、歯茎や口腔粘膜からの出血、鼻出血、黒い便が出る(消化管出血)、紅茶のような尿が出る(尿路出血)といった症状が見られたら、早急に動物病院を受診するようにしましょう。