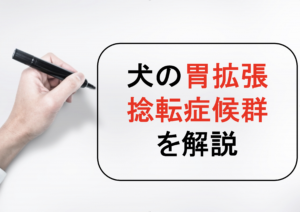「最近はあまり聞かない病気なのかな?」と思うかもしれませんが、犬ジステンパーは決して過去の病気ではありません。
ワクチンの普及によって発症例は減少していますが、予防接種を受けていない子犬や集団飼育の現場では、いまも発生が報告されています。
犬ジステンパーは、命に関わる重篤な感染症であり、回復しても後遺症として神経症状が残る可能性があるため、油断できません。
この病気は、「コアワクチン」と呼ばれる最も重要な予防接種の対象のひとつです。
コアワクチンとは、感染すると重症化しやすく、死亡率が高い・広く蔓延する可能性がある感染症に対して、すべての犬が接種すべきとされるワクチン群のことです。犬では、ジステンパー、パルボウイルス感染症、アデノウイルス感染症などがこれに該当します。
今回は、そんなコアワクチンで予防可能な重大感染症「犬ジステンパー」について、原因や症状、診断・治療、そして予防のポイントまでわかりやすく解説します。
この記事はこんな方におすすめです
- 子犬をこれから迎える予定の方・迎えたばかりの方
- ワクチンの重要性について改めて知りたい方
- 保護犬やワクチン歴のわからない犬を飼っている方
- 犬ジステンパーの症状や治療について詳しく知っておきたい方
犬ジステンパーとは
犬ジステンパーとは、犬ジステンパーウイルスによって起こるウイルス性感染症です。
主に3~6ヶ月齢の子犬に多く見られ、感染すると発熱、呼吸器・消化器症状、さらには神経症状に進行する可能性もあります。
症状の程度には幅があり、軽度で済む場合もあれば、重度の場合は死亡に至ることもあります。
特に神経症状を呈した場合は、予後が悪くなる傾向にあります。
原因
犬ジステンパーの原因は、パラミクソウイルス科モルビリウイルス属の犬ジステンパーウイルス(CDV)です。
このウイルスは、感染した犬の鼻水や咳などの飛沫を通じて広がる「飛沫感染」が主な感染経路です。
また、糞尿や分泌物、皮膚の接触などでも感染することがあります。
イヌ科(犬、キツネ、コヨーテなど)だけでなく、フェレットやアライグマなど他の動物にも感染することがありますが、人にうつることはありません。
犬ジステンパーの症状
犬ジステンパーは、特にワクチン未接種の若齢犬で疑われる感染症です。
典型的には、粘膜症状(鼻水・目やに・咳・嘔吐・下痢)に続いて、回復期またはその後に神経症状が出る場合に強く疑われます。
この神経症状として現れる顔面のチックや運動障害、てんかん発作は、犬の「症候性てんかん」の原因となることもあります(詳しくは [こちらの記事をご覧ください])。
診断には以下の検査が用いられます:
- PCR検査(ウイルス遺伝子の検出)
- 血清抗体価の測定
- 脳脊髄液中の抗体検出
また、犬ジステンパーウイルスは、感染後およそ2週間で体外へのウイルス排出が始まり、60〜90日間続くとされています。
一方で、十分な免疫をもつ犬では症状が出ず、感染後14日以内にウイルスを排除できるとされており、これにより神経症状への進行リスクも大幅に低くなります。
💡 補足:
ワクチン接種歴も参考になりますが、接種していてもまれに感染や発症が起こることがあるため、完全な除外診断にはなりません。
犬ジステンパーの診断
犬ジステンパーは、特にワクチン未接種の若齢犬で疑われる感染症です。
典型的には、粘膜症状(鼻水・目やに・咳・嘔吐・下痢)に続いて、回復したかに見えた数日後に神経症状が現れるという経過をたどることがあります。
たとえば、「1週間ほど前に風邪のような症状があり一度元気になったのに、その後チックや発作が出てきた」というケースは、ジステンパーによる神経症状の可能性が高いとされます。
このようなケースでは、以下の検査によって診断を進めます:
- PCR検査(ウイルス遺伝子の検出)
- 血清抗体価の測定
- 脳脊髄液中の抗体検出
また、犬ジステンパーウイルスは、感染後およそ2週間で体外へのウイルス排出が始まり、60〜90日間続くとされています。
一方で、十分な免疫をもつ犬では症状が出ず、感染後14日以内にウイルスを排除できるとされており、これにより神経症状への進行リスクも大幅に低くなります。
💡 補足:
ワクチン接種歴も参考になりますが、接種していてもまれに感染や発症が起こることがあるため、完全な除外診断にはなりません。
犬ジステンパーの治療
ジステンパーに対する特効薬はなく、基本は対症療法となります。具体的には:
- 抗菌薬:細菌性肺炎などの二次感染対策
- 輸液:脱水の補正
- 抗てんかん薬:神経症状への対応
💡 補足:
神経症状が出た場合は、完治が難しく、後遺症として長期のてんかん管理が必要になることもあります。
予後
犬ジステンパーの予後は、感染した犬の免疫力と、神経症状の有無によって大きく左右されます。
- 十分な免疫を持つ犬(ワクチン接種済みなど)では、無症状または軽い症状のみで経過し、感染後14日以内にウイルスを排除できるとされています。この場合、神経症状に進行する可能性は非常に低く、予後は良好です。
- 一方、免疫力が不十分な犬やワクチン未接種の犬では、ウイルスが全身に広がり、重篤な呼吸器・消化器症状、さらには神経症状まで発展するリスクが高くなります。
感染後2週間ほどでウイルスの排出が始まり、60〜90日間にわたって体外にウイルスを出し続けることがあるため、周囲の感染リスクも注意が必要です。
また、一度回復した後に遅れて神経症状(てんかん、チック、運動障害など)が出る場合もあり、この場合は後遺症として生涯にわたり管理が必要になる可能性があります。
💡 ポイント:
ジステンパーからの生還率は低くはありませんが、「後遺症なく元気に過ごせるかどうか」は、いかに早期に発見し、適切なケアを受けられるかにかかっています。
まとめ
犬ジステンパーは、かつて広く恐れられていた感染症ですが、いまも油断できない病気です。
ワクチンによって発症は減っていますが、ペットショップやブリーダーの環境、保護犬などでは集団感染が起こる可能性もあります。
回復しても、神経症状が後から出ることがあるため、注意深い観察が必要です。
🛡予防のポイント
- コアワクチン(混合ワクチン)を必ず定期的に接種すること
- ワクチン歴の不明な犬を迎える際は、早めの健康診断と抗体チェック
- 子犬の社会化期(~16週齢)は、衛生的な環境で過ごすことが重要です
愛犬の健康を守るためにも、ジステンパーという病気を「知っておくこと」こそが、最大の予防となります。不安なことがあれば、早めに獣医師に相談しましょう。