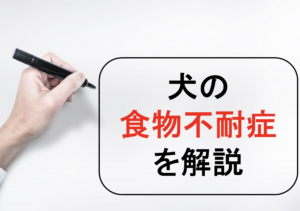愛犬が突然けいれん発作を起こす――
そんな光景を目にした飼い主さんは、驚きと不安でいっぱいになることでしょう。
犬のてんかん発作は、決して珍しいものではなく、日本では犬の約1〜2%に発症すると報告されています。なかでも比較的若い犬に多く見られるのが「特発性てんかん」です。
この記事では、特発性てんかんの特徴や診断のポイント、治療、そして予後までを、現役の獣医師がわかりやすく解説します。発作を起こした愛犬への対応に不安がある方や、てんかんについて正しい知識を身につけたい方は、ぜひ最後までお読みください。
この記事はこんな方におすすめです
- 動物病院で「特発性てんかん」と診断された、または疑われている犬の飼い主さま
- 繰り返すけいれんや発作に悩む愛犬をお持ちの方
- 犬のてんかんについて学びたい獣医学生や動物看護師の方
犬の特発性てんかんとは
てんかんとは、大脳の神経細胞が異常に興奮し、けいれん発作を引き起こす慢性の脳疾患です。原因により「特発性てんかん」と「症候性てんかん」の2つに分類されます。
- 特発性てんかん:脳に明確な器質的異常は認められず、遺伝的な要因が関与していると考えられるタイプ。1〜5歳の若い犬に多く見られます。
- 症候性てんかん:脳腫瘍や脳炎、奇形など、器質的な脳の病変が原因となって発作が起きるタイプ。1歳未満や6歳以上の犬に多く見られます。
➡️ [関連記事:犬の症候性てんかんはこちら]
なお、血糖値の異常や中毒など、脳以外の原因による発作は「反応性てんかん(急性症候性発作)」と呼ばれ、分類上てんかんとは区別されます。
原因
特発性てんかんには遺伝的素因があるとされ、以下の犬種でよくみられます。
ビーグル、シベリアン・ハスキー、シェットランド・シープドッグ、ラブラドール・レトリバー、ゴールデン・レトリーバー、ジャーマン・シェパードなど。
特発性てんかんの症状
発作は大きく「全般発作」と「部分発作」に分類されます。
全般発作では、脳全体に異常な電気活動が広がるため、全身が突っ張るように硬直する「強直発作」や、全身がガクガクとけいれんする「間代発作」など、全身性の症状がみられます。
一方、部分発作は脳の一部だけが異常に興奮するため、顔面や四肢の一部など、身体の限られた部位にだけピクピクとしたけいれんが起こるのが特徴です。
また、てんかん発作は段階を追って出現するのが特徴で、
- 発作前:そわそわする、落ち着きがない
- 発作中:けいれん・意識消失・流涎・排泄など
- 発作後:意識混濁・ふらつき・過食など
と進行します。
発作が起きた時は
愛犬がてんかん発作を起こしている場面に遭遇したら、まずは慌てずに落ち着くことが大切です。
発作中は犬が自分を制御できない状態にあるため、周囲の安全を確保し、家具や壁などにぶつからないようクッションや毛布で体を保護してあげましょう。
そして、絶対に犬の口の中に手を入れないようにしてください。
発作中の犬は意識がもうろうとしており、飼い主を認識できなくなっているため、反射的に噛みついてしまうことがあり、大けがのリスクがあります。
また、「舌を噛んで窒息するのでは」と心配されることがありますが、犬のてんかん発作ではその可能性は非常に低いため、無理に口を開けたり何かを咬ませたりする必要はありません。
発作が短時間でおさまる場合は、自宅で様子を見ても構いませんが、数分以上続く場合や連続して何度も発作を起こす場合は緊急事態の可能性もあるため、すぐに動物病院を受診してください。
特発性てんかんの診断
犬の特発性てんかんは、除外診断によって確定されることが多い病気です。
つまり、「発作を起こす他の病気がないこと」を確認することで、最終的に特発性てんかんと診断されます。
まずは、問診が非常に重要です。以下のような情報を動物病院に伝えられると、診断の精度が高まります:
- 初めて発作が起きた年齢
- 発作の持続時間や回数
- 発作の前後の様子(落ち着きがない、ふらつく、意識がもうろうとする等)
- 発作時の時間帯や周囲の状況(食事中、睡眠中など)
発作中の様子をスマートフォンで動画撮影しておくと、診察時に非常に役立ちます。
また、身体検査や神経学的検査に加えて、血液検査で代謝性疾患や中毒などの「反応性てんかん」を除外し、必要に応じてMRI検査や脳脊髄液検査を行って、脳炎や脳腫瘍といった「症候性てんかん」の可能性も確認します。
そのうえで、特発性てんかんが最も疑われる場合に、抗てんかん薬の投与を開始することになります。
特発性てんかんの治療
特発性てんかんは完治が難しい病気ですが、抗てんかん薬によって発作の回数や重症度を抑えることが可能です。
薬の選択や投与開始のタイミングは、発作の頻度や重症度、発作後の回復の様子などを総合的に評価して判断します。
治療開始の目安としては、以下のような状況が挙げられます:
- 3か月以内に2回以上の発作がある
- 1年の間に複数回の発作日がある
- 発作が長く続く、または発作が止まらない(重積発作)
- 発作後の回復に時間がかかる、または異常な行動が見られる
- MRI検査などで脳病変が否定され、特発性てんかんの可能性が高いと判断された
投薬を開始したら、継続して服薬することが非常に大切です。
抗てんかん薬は急にやめると発作が悪化する危険があるため、獣医師の指導のもとで定期的に血中濃度の測定を行いながら、適切な量を維持していきます。
予後について
特発性てんかんを抱える犬でも、適切な治療と生活管理によって長期的に安定した生活を送ることは十分可能です。
ただし、発作のコントロールには個体差があり、薬が効きにくいケース(難治性てんかん)もあります。
そのため、飼い主と獣医師がしっかりと連携しながら治療を続けていくことが何より重要です。
まとめ
犬の「特発性てんかん」は、比較的若い年齢で発症し、遺伝的素因が関与すると考えられている脳の慢性疾患です。
完治は難しいものの、抗てんかん薬の服用によって発作をコントロールし、普段通りの生活を送ることが可能です。
発作時の様子を落ち着いて観察し、記録・動画撮影しておくことは、診断や治療方針の決定に大いに役立ちます。
また、投薬開始後は定期的な通院と血中濃度のチェックを継続し、愛犬にとって最も適した管理を行っていくことが大切です。
発作に戸惑い、不安に思う飼い主さまも多いと思いますが、特発性てんかんは正しい知識とサポートがあれば、共に穏やかな生活を送ることができる病気です。