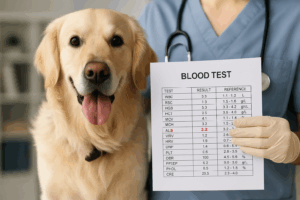動物病院で愛犬の血液検査を受けた際、検査結果の見方に戸惑ったことはありませんか?
本記事では、血液検査の「総コレステロール(T-cho)」の異常についてわかりやすく解説します。
ぜひ、愛犬の検査結果を片手にご覧ください。
※ご注意ください
・正常値は検査機器や検査会社によって異なりますので、血液検査の用紙に記載された基準値を参照してください。
・検査結果が基準値を外れていても、必ずしも病気とは限りません。担当の獣医師に詳しく説明を受けましょう。
総コレステロール(T-Cho)とは
総コレステロールとは、血液中に存在するすべてのコレステロールの合計値を示します。具体的には、いわゆる「善玉コレステロール」とされるHDLコレステロールや、「悪玉コレステロール」とされるLDLコレステロールなどを含んだ、血中コレステロールの総量です。
血中のコレステロールは、約7割が体内(主に肝臓)で合成され、残り約3割が食事から摂取されるとされています。従って、血中コレステロールの異常は食事の影響だけでなく、肝臓機能や内分泌疾患の影響を受けることも多く、原発性あるいは続発性の脂質代謝異常として重要な臨床指標となります。
| 検査会社 | 基準値 |
|---|---|
| 富士フィルムモノリス | 85~337 mg/dl |
| アイデックス | 110〜320 mg/dl |
総コレステロール(T-Cho)高値の原因
血液中のコレステロール濃度が基準値より高くなる状態は「高コレステロール血症」と呼ばれます。犬では、さまざまな代謝や内分泌の異常によってこの状態が生じます。
特に、脂質の合成が過剰になる状況や、脂質の分解・排泄が障害される状態でコレステロールが高くなる傾向があります。これは、内分泌疾患や肝胆道系の異常、また腎疾患などの慢性疾患によって起こることがあり、体の中でコレステロールが必要以上に産生されたり、うまく処理できなくなったりすることで血中に蓄積されるためです。
また、一部の犬種では遺伝的に脂質代謝に異常をきたしやすい体質があることも知られており、特に無症状であっても血中コレステロールが慢性的に高くなるケースもあります。
このようなコレステロール高値は、特定の病気の進行と関連していることが多いため、単なる食事性の変動と安易に考えず、原因精査が必要となります。
| 総コレステロール(T-Cho)高値の原因 |
| ネフローゼ症候群 甲状腺機能低下症 糖尿病 副腎皮質機能低下症(クッシング症候群) 急性膵炎 胆汁うっ帯(閉塞性) 遺伝(ミニチュアシュナウザーの特発性高脂血症 |
総コレステロール(T-Cho)低値の原因
血液中のコレステロール濃度が基準値より低くなる状態は「低コレステロール血症」と呼ばれます。犬においては比較的まれな異常ですが、体内でのコレステロール合成が著しく低下する状況や、コレステロールの喪失が亢進する状態でみられます。
特に、重度の肝機能障害では、コレステロールを合成する能力そのものが低下し、血中濃度が減少します。また、腸管からの吸収不良があると、コレステロールの取り込み自体が不十分になり低値となることがあります。さらに、タンパク喪失性疾患などによって血漿中の脂質が漏れ出す場合にも、間接的にコレステロールの低下が起こることがあります。
また、炎症性疾患や悪性腫瘍の一部においても、代謝異常の一環としてコレステロールが低下するケースがあります。
コレステロールの低下は、進行性疾患のマーカーとなっていることもあるため、単なる栄養状態の問題と決めつけず、背景にある病態を慎重に見極めることが重要です。
| 総コレステロール(T-Cho)低値の原因 |
| 甲状腺機能亢進症 アジソン病 肝障害 |
まとめ
犬の血液検査項目のひとつである「総コレステロール(T-Cho)」は、主に肝機能、内分泌系、栄養状態などを反映する重要な指標です。
T-Choが高値を示す場合には、甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)などのホルモン異常や、ネフローゼ症候群、糖尿病、胆汁うっ滞といった慢性疾患が背景にある可能性があります。特にネフローゼでは、体外にタンパクが失われるため、肝臓がコレステロールを代償的に合成して高値を示すのが特徴です。
一方で、T-Choが低値を示す場合には、重度の肝障害、吸収不良症候群、悪液質など、栄養障害や肝機能不全が疑われます。低コレステロール血症は、高値に比べて注目されにくいですが、時に深刻な基礎疾患のサインとなるため注意が必要です。
異常値が見つかった場合は、追加の血液検査やホルモン検査、画像診断などを組み合わせて原因を特定し、早期に対応することが重要です。
血液検査の結果に不安があるときは、遠慮せずに動物病院で獣医師に相談してみましょう。