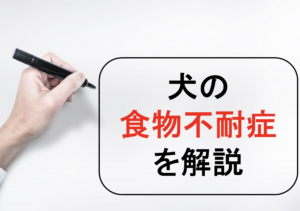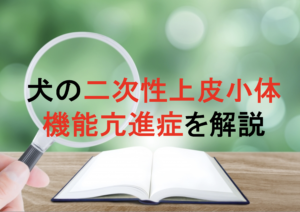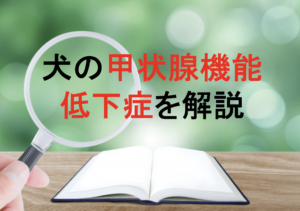この記事では、犬のバベシア症について、原因・症状・診断・治療・予防法までを、獣医師がわかりやすく解説しています。
犬のバベシア症は、マダニが媒介する感染症の中で特に重篤であり、適切な治療が行われないと死に至ることもある非常に危険な病気です。しかし、日常的なマダニ予防により防ぐことが可能な疾患でもあります。
この記事を読むことで、バベシア症に対する正しい知識と対策が身につくよう構成していますので、ぜひ最後までお読みいただけると嬉しいです。
対象読者
- 動物病院で犬のバベシア症と診断された、あるいは疑われている犬の飼い主さん
- 発熱や貧血などの体調不良が続いている犬の飼い主さん
- バベシア症を含むマダニ媒介疾患について学びたい獣医学生や動物看護師の方
バベシア症とは
バベシア症は、バベシア属の原虫が赤血球に寄生することによって起こる感染症です。犬においては、主にマダニによって媒介されることで知られており、特に西日本を中心に多く発生が報告されています。
バベシア原虫に感染すると、赤血球が破壊されるため、貧血や黄疸などの血液系の異常が起こります。重症化すると、生命を脅かすこともある重篤な疾患です。
感染後の発症には数日から数週間の潜伏期間があり、突然元気消失や食欲不振などがみられることもあります。マダニの予防が非常に有効な感染予防手段であり、飼い主の意識と対応が発症リスクを大きく左右します。
バベシア症の原因
犬のバベシア症の原因となる原虫は、主に以下の2種類が知られています。
- バベシア・ギブソニー(Babesia gibsoni)
- 日本国内では最も一般的な型で、西日本を中心に高い発生率が報告されています。
- 小型(1〜3μm)の原虫で、赤血球に寄生し溶血性貧血を引き起こします。
- 主な感染経路はマダニの吸血ですが、輸血、闘犬による出血を伴う接触、まれに母子感染などでも感染が成立することがあります。
- バベシア・カニス(Babesia canis)
- 日本では沖縄地方など一部地域で報告があります。
- ギブソニーよりも大型で、症状や治療法に若干の違いがありますが、国内での発症例は少数です。
バベシア原虫に感染したマダニが犬に2~3日以上寄生して吸血すると、唾液中に含まれる原虫が血中へと侵入します。このため、マダニ予防薬を用いた早期駆除が非常に重要です。
また、感染後は体内からの完全な駆虫が困難で、ストレスや免疫低下をきっかけに再発することがあるため、生涯にわたる管理が必要になることもあります。
バベシア症の症状
犬のバベシア症は、赤血球の破壊(溶血)が主な病態であるため、それに関連する症状が多くみられます。発症の程度はさまざまで、軽度の体調不良から急激な貧血によるショック症状まで幅広く、以下のような臨床徴候が報告されています。
- 元気消失(沈うつ)
- 食欲不振
- 粘膜の蒼白(貧血による)
- 黄疸(ビリルビン増加に伴う)
- 発熱
- 脾臓やリンパ節の腫大
- 運動不耐性(すぐに疲れる)
バベシア症の診断
犬のバベシア症では、以下のような血液・尿検査の異常が確認されることが多く、最終的には血液塗抹またはPCR検査によって確定診断が行われます。
血液検査でみられる異常
- 溶血性貧血:赤血球が破壊されることで、貧血が生じます。
- 血小板減少症:血小板数の低下が認められます。出血傾向の原因となることがあります。
- CRP(C反応性蛋白)の上昇:体内の炎症反応を示す指標であり、ほとんどの症例で上昇が確認されます。
- 白血球数の変動:多くの場合、白血球は炎症に反応して増加しますが、まれに減少が見られるケースもあります。

尿検査でみられる異常
- ビリルビン尿:溶血によって発生したビリルビンが尿中に排出されます。
- ヘモグロビン尿:赤血球破壊によって遊離したヘモグロビンが尿中に排出されることがあります。
確定診断
以下のいずれか、または両方の検査でバベシア症が確定診断されます。
- 血液塗抹検査:顕微鏡で赤血球内にバベシア原虫(Babesia gibsoniまたはBabesia canis)の虫体を直接確認します。ただし、虫体が少ない場合は検出が困難です。
- PCR検査(遺伝子検査):高感度でバベシアのDNAを検出でき、血液塗抹で検出できなかった軽度の感染でも診断可能です。
バベシア症の治療
犬のバベシア症に対する治療は、原虫の駆除を目的とした初期治療と、再発を防ぐ維持治療の2段階に分かれます。重度の貧血が認められる場合は、輸血を行うこともあります。
初期治療(駆除目的)
バベシア原虫を体内から排除するための治療です。主に以下の2つの薬剤が使用されます。
① ジミナゼン(ジミナゼンアセチュレート)
- メリット:費用が比較的安価であること
- デメリット:副作用が強く、注射部位の疼痛、肝障害・腎障害、小脳出血などが報告されています。また、原虫の駆除率が低く、再発するリスクがあります。
② アトバコン
- メリット:副作用が少なく、治療効果も高いとされています
- デメリット:薬価が高く、治療費が高額になる傾向があります。また、耐性が生じる可能性も指摘されています。
維持治療(再発予防)
バベシア原虫は、治療後も体内に潜伏することがあり、ストレス・手術・免疫抑制などをきっかけに再発することがあります。そのため、再発予防として複数の薬剤を組み合わせた長期的な維持療法が行われることがあります。
- 維持療法の目安期間は 約3ヶ月間 とされています。
- 再発リスクの高い犬では、生涯にわたって定期的なモニタリングが必要になることもあります。
補助療法:輸血
重度の貧血が認められ、全身状態が悪化している場合には、輸血を行い赤血球量を一時的に回復させます。輸血は対症療法であり、バベシア原虫の駆除にはつながりません。
バベシア症の予後
犬のバベシア症は、適切な治療を行っても原虫の完全な排除は困難とされており、多くの場合、体内に潜伏感染が残ります。そのため、再発のリスクが生涯にわたって続くという点が大きな特徴です。
再発は以下のようなタイミングで起こりやすいとされています。
- 強いストレスを受けたとき
- ステロイドなどの免疫抑制剤を使用したとき
- 手術(特に脾臓摘出など)を受けたとき
- 他の病気で免疫力が低下したとき
バベシア症に感染した犬の中には、治療にうまく反応し、長期的に安定した生活を送れる場合もありますが、再発を繰り返すケースや重度の貧血によって命を落とすケースもあるため、油断せず継続的なケアと予防が重要です。
バベシア症の予防
犬のバベシア症は、予防が非常に重要な病気です。特に、主な感染経路であるマダニの吸血を防ぐことで、高確率で感染を防ぐことができます。
マダニは草むらや山林、公園などに生息しており、犬がそこを散歩することで寄生する可能性があります。バベシア原虫を含んだマダニの唾液が体内に注入されるには吸血後2~3日程度が必要とされているため、マダニが寄生しても早期に駆除されれば感染を防ぐことが可能です。
そのため、以下のような対策が推奨されます:
- マダニ予防薬(スポット剤や経口薬)を定期的に使用する
- 草むらへの立ち入りを避ける、帰宅後に身体をチェックする
- 多頭飼育や外出の多い犬では特に予防薬の継続が重要
さらに、輸血や闘犬による咬傷、母子感染といったマダニ以外の感染経路もあります。これらを防ぐために:
- 血液ドナーはバベシアのスクリーニングを行う
- 闘犬などによる接触を避ける
- 繁殖犬に感染がないか確認する
といった管理が必要です。
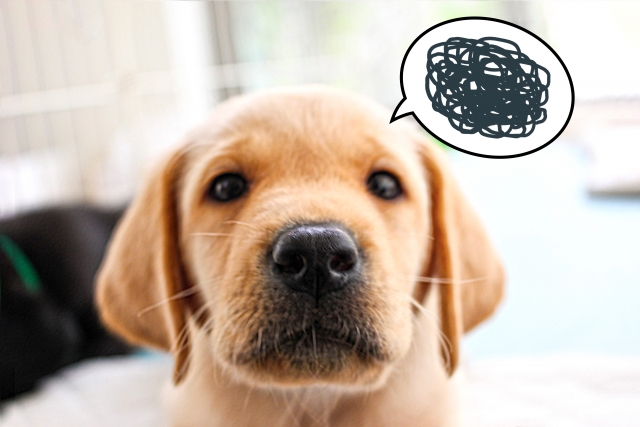
まとめ
この記事では、犬のバベシア症について、原因・症状・診断・治療・予防の観点から解説しました。
犬のバベシア症は、赤血球に寄生するバベシア原虫による感染症で、マダニが主な感染経路です。特に日本では、西日本を中心にBabesia gibsoniによる症例が多く見られます。稀に輸血や咬傷などによる感染も報告されています。
症状としては、溶血性貧血・発熱・元気消失・粘膜蒼白・黄疸などがみられ、重症化すると死に至ることもあります。また、一度感染すると完全な駆虫は難しく、生涯再発のリスクを抱えることになるため、長期的な管理が必要です。
診断には血液検査やPCR検査が有効であり、治療は原虫の駆除に加え、再発防止のための維持療法、必要に応じた輸血などが行われます。
しかし、この疾患は適切なマダニ予防により十分に防げる病気でもあります。月に1回の予防薬や生活環境の管理を通じて、愛犬を重大な感染症から守ることができます。
バベシア症について不安な点がある場合や、疑わしい症状がみられた場合には、早期に動物病院を受診し、適切な検査と治療を受けることが大切です。