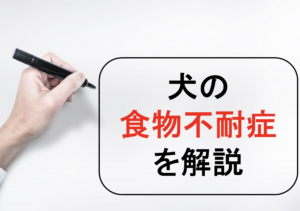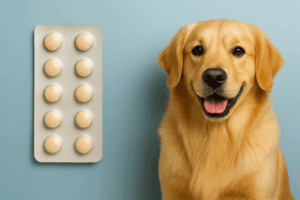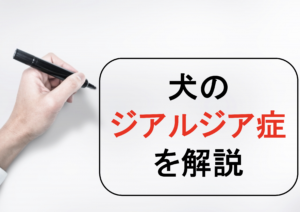この記事では、犬の腸リンパ管拡張症について、原因・症状・診断・治療を、現役獣医師がわかりやすく解説しています。
本記事を読むだけで、腸リンパ管拡張症の基本がすぐに理解できるように構成しています。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。
対象読者
- 腸リンパ管拡張症と診断された、あるいは疑われている犬の飼い主
- 長期間下痢が続いて悩んでいる犬の飼い主
- 血清検査で低アルブミン血症を指摘された犬の飼い主
- 腸リンパ管拡張症に関心のある獣医学生や動物看護師
腸リンパ管拡張症とは
腸リンパ管拡張症とは、消化管や腸間膜に存在するリンパ管が異常に拡張し、そこからリンパ液が漏れ出したり、リンパ管自体が破裂してしまう病気です。犬における蛋白漏出性腸症(PLE)の主な原因のひとつとされています。
リンパ系とは
リンパ系は、体内の余分な組織液(間質液)を回収して静脈へ戻す役割を持つ「導管ネットワーク(リンパ管)」と、免疫機能を担う「リンパ節」などのリンパ組織で構成されています。主に以下の3つの働きがあります。
- 組織からの余剰液の回収
- 小腸で吸収された脂質(長鎖脂肪酸)を乳糜(にゅうび)として血流へ運ぶ
- 免疫細胞(リンパ球など)の産生と移送
腸リンパ管拡張症の発症機序
この病気では、以下のような過程で症状が進行します。
- 消化管や腸間膜のリンパ管が異常に拡張する
- リンパの流れが滞る
- 漏出や破裂によってリンパ液が消化管内に漏れ出す
- そのリンパ液にはアルブミンやコレステロールなどの重要なタンパク・脂質が豊富に含まれているため、消化管に漏れることで体内での保持が困難となる
- 結果として低アルブミン血症や低コレステロール血症を引き起こす
この疾患はヨークシャーテリアやマルチーズなどの犬種でやや多く見られるとされていますが、どの犬種にも発症する可能性があります。
原因
腸リンパ管拡張症には「原発性(一次性)」と「続発性(二次性)」の2つの発症形態があります。ただし、実際には両者の明確な区別が難しいケースも少なくありません。
原発性腸リンパ管拡張症
先天的あるいは遺伝的な要因が関与していると考えられており、リンパ管の構造異常や機能異常によって、リンパ液の流れがうまくいかなくなります。発症時期は若齢であることが多く、小型犬種で比較的よく見られます。
続発性腸リンパ管拡張症
何らかの基礎疾患によって二次的にリンパ管が閉塞されたり、リンパの流れが阻害されることで発症します。主な原因は以下の通りです。
- 炎症性腸疾患(IBD):腸管の慢性的な炎症によりリンパの流れが障害される
- リンパ腫などの腫瘍性疾患:腸間膜リンパ節や腸壁の腫大・閉塞によりリンパ還流が妨げられる
- 右心不全・門脈圧亢進症:静脈圧の上昇によってリンパ管の排出が阻害される
このように、原発性では体質的な要因が、続発性では別の病気に伴って腸リンパ管拡張症が引き起こされると理解するとよいでしょう。
腸リンパ管拡張症の症状
腸リンパ管拡張症の症状は多彩で、以下のようなものが見られますが、犬によっては消化器症状がまったく見られないこともあります。
- 慢性的な下痢(特に軟便〜水様便)
- 体重減少
- 食欲低下
- お腹に水が溜まる(腹水)や胸水の貯留
- 四肢の浮腫(むくみ)
これらの症状は、腸管内へ漏出したリンパ液中のアルブミンや脂質が失われることで、血中タンパク質や脂質が減少することによって発生します。
特に血清アルブミンが1.5 g/dl未満になると、血管内の浸透圧が低下して腹水や浮腫などの臨床症状が目立つようになります。
さらに、腸間膜のリンパ管が破裂したり重度に炎症を起こすと、リンパ液の再吸収が困難となり悪循環に陥ることもあります。進行すると、栄養不良や免疫力低下を引き起こす原因にもなり得るため、早期の診断・治療が大切です。
腸リンパ管拡張症の診断
腸リンパ管拡張症の診断には、血液検査・超音波検査・内視鏡検査・病理組織学的検査など、複数の検査を組み合わせて総合的に判断します。
血液検査
以下の異常所見が特徴的です。
- 低タンパク血症
- 低アルブミン血症
- 低コレステロール血症
これらの所見は、腸管内に漏れ出したリンパ液によって血中からタンパク質や脂質が失われていることを示しています。
超音波検査
小腸の粘膜層に見られる高エコーの線状パターンは、腸リンパ管拡張症を強く示唆する所見とされています。また、リンパ腫などの他の蛋白漏出性腸症の原因を探る上でも非常に重要な検査です。
内視鏡検査および生検
確定診断には、腸粘膜からの生検による病理組織学的検査が必要です。拡張したリンパ管が組織内に確認されれば、診断が確定します。
鑑別診断
低タンパク血症を示す他の疾患も念頭に置く必要があります。特に以下のような状態と鑑別することが重要です:
- 出血や浸出液によるタンパク喪失
- 肝不全による産生低下
- 腎疾患(ネフローゼ症候群など)
- 栄養不良、吸収不良、免疫異常
| 低タンパク血症の原因 |
| 出血による喪失 広範囲の皮膚の浸出性病変※ 腸からの漏出腸(リンパ管拡張症など) 腹水や胸水の貯留 過剰輸液 肝不全 腎臓からの漏出(ネフローゼ症候群など) 栄養の吸収不良や消化不良 飢餓による栄養失調 先天性/後天性免疫異常 |
※滲出性病変:急性炎症の時にみられる炎症
腸リンパ管拡張症の治療
腸リンパ管拡張症の治療は、原発性か続発性かによってアプローチが異なります。
食事療法(第一選択)
基本となるのは低脂肪かつ良質なタンパク質を含む食事です。
- 長鎖脂肪酸(LCT)はリンパ流量を増やすため制限
- 中鎖脂肪酸(MCT)は門脈吸収されやすく、利用されることもある
- 栄養の吸収効率が高く、消化しやすいフードが望ましい
市販の低脂肪療法食がまずは選択されますが、反応が乏しい場合は、超低脂肪の家庭調理食(例:ささみ+白米やじゃがいも)に切り替えることもあります。ただし家庭調理食は栄養バランスに注意が必要です。
グルココルチコイド(ステロイド)
食事のみで改善しない場合、プレドニゾロンなどのステロイド投与を行います。反応があれば、段階的に用量を減らしながら継続します。
例:2〜4週ごとに25〜50%ずつ減量。ただし、完全な中止は難しいケースが多く、生涯投与が必要なこともあります。
腹水に対する治療
アルブミン値が1.5 g/dl以下になると腹水・胸水・浮腫がみられるようになります。
- 利尿薬の使用(例:フロセミド)
- 穿刺による腹水の排出
を組み合わせて管理します。
輸血
理論的にはタンパク補給になりますが、輸血によるアルブミン上昇効果は限定的で、コストや効果の点から一般的には推奨されません。
抗血栓療法
蛋白漏出性腸症は血栓塞栓症のリスクを高めますが、腸リンパ管拡張症での予防的抗凝固療法の有用性は確立していません。必要性については症例ごとの判断が求められます。
その他の治療
ステロイド単独で効果が乏しい場合には、アザチオプリンやシクロスポリンなどの免疫抑制薬が使用されます。
また、低コバラミン血症が併発している場合は、ビタミンB12の補充も行います。
予後
腸リンパ管拡張症の予後(病気の経過や見通し)は個体差が大きく、一概には言えません。ただし、長期にわたる管理が必要になるケースが多いという点は共通しています。
- 早期診断と適切な治療開始により、長期的に良好な生活を送れる犬も多くいます。
- 一方で、消化器症状が強い場合や体重減少が顕著な場合、治療への反応が乏しい場合には、生存期間が短くなる可能性があることも報告されています。
- 特に、低アルブミン血症が重度で腹水や胸水が頻繁に貯留するような症例では、管理が難しくなる傾向があります。
腸リンパ管拡張症は完治が難しい慢性疾患と捉え、継続的な観察と生活管理を行っていくことが大切です。
まとめ
腸リンパ管拡張症は、腸管のリンパ管が異常に拡張し、リンパ液が腸内に漏れ出ることで、タンパク質や脂質が失われる病気です。これは犬の蛋白漏出性腸症の主な原因の一つであり、慢性的な下痢や体重減少、腹水・胸水などの症状として現れることがあります。
診断には、血液検査や超音波検査、内視鏡による生検などを用いて、他疾患との鑑別を含めた精査が重要です。
治療の中心は食事管理と薬物療法です。特に脂肪を制限した食事療法が基本であり、必要に応じてステロイドや免疫抑制剤を使用することもあります。
この病気は一度治療すれば完治するものではなく、生涯にわたる管理が必要になる場合が多いです。しかし、早期発見と適切な治療により、症状をコントロールしながら生活の質を維持することは十分に可能です。
もし愛犬に慢性的な下痢や体重減少、低アルブミン血症などの異常がみられた場合は、早めに動物病院での検査と診察を受けることをおすすめします。