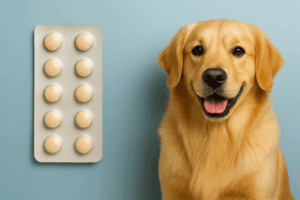この記事では、犬の炎症性腸疾患(IBD)について原因、症状、診断そして治療を、現役獣医師が解説しています。
最後まで読むだけで、抗菌薬反応性腸症について誰にでもすぐに理解できるように作成しているので、是非一度目を通していただけると嬉しいです。
抗菌薬反応性腸症とは
抗菌薬反応性腸症は、抗菌薬に反応し改善する下痢と定義されます。
細菌感染が無いにも関わらず、抗菌薬を投与すると改善する下痢が知られており、この病気を「小腸細菌過剰症」と呼んでいました。しかし、研究によって小腸内の細菌が必ずしも増加していないことが明らかとなりました。そこで近年は、「小腸細菌過剰症」よりも「抗菌薬反応性腸症」と呼ぶことが多くなりました。
原因
抗菌薬反応性腸症は、原発性と二次性に分類されます。
原発性抗菌薬反応性腸症
消化管の細菌感染(カンピロバクター属、クロストリジウム属、サルモネラ属など)が除外されている犬でも、抗菌薬の投与で下痢の改善がみらる場合があります。よって、消化管の細菌感染による単純な感染症では無いと考えられています。
この病気の詳しい仕組みは分かっていませんが、以下の原因が考えられています。
- 腸管内の細菌の著しい増加や腸粘膜の細胞に対する障害
- エンテロトキシンの分泌や腸粘膜における透過性の亢進
- IgA欠損などの免疫異常
原発性の抗菌薬反応性腸症は、全ての犬で起こる可能性がありますが、若齢の大型犬(特にジャーマンシェパード)とビーグルにおける発生が多いようです。
二次性抗菌薬反応性腸症
以下の基礎疾患に続発して、発症する可能性があります。
- 消化管の閉塞性疾患や運動性低下
- 膵外分泌不全
- 胃酸の分泌減少
- 消化管バイパス手術

抗菌薬反応性腸症の症状
慢性下痢と体重減少がよくみられ、時に嘔吐もみられます。
3週間を超えても続く下痢のこと
下痢は、小腸性下痢と大腸性下痢に分類されます。両者の区別は以下の通りです。
- 小腸性下痢:便の回数は変わらないが1回の便の量が多く、体重が減ってくることが特徴
- 大腸性下痢:1回の便の量は少ないでが便の回数が多くなるが、体重の減少がみられないのが特徴
抗菌薬反応性腸症は、小腸性下痢を起こす病気として知られています。

抗菌薬反応性腸症の診断
原発性の抗菌薬反応性腸症は、以下の診断基準が提唱されています。
- 抗菌薬の投与によって速やかに症状が改善すること
- 抗菌薬の減量または中止により症状が再発すること
- 再発後、抗菌薬の再投与により再び改善すること
- 便検査、血液検査、画像検査、腸粘膜の生検などで下痢を起こす明らかな疾患が認められないこと
血液中の葉酸とコバラミン濃度の測定では、コバラミン濃度の低下および葉酸濃度の上昇がみられることがあります。

抗菌薬反応性腸症の治療
抗菌薬反応性腸症の治療は、原発性と二次性で異なります。
原発性の抗菌薬反応性腸症に対しては、以下のいずれかの抗菌薬の投与が推奨されています。
- タイロシン(商品名:タイラン)
- メトロニダゾール(商品名:フラジール)
- オキシテトラサイクリン(商品名:ミノペン)
タイロシンは長期に投与しても比較的安全な薬剤と考えられています。メトロニダゾールは、高用量で用いる場合、神経症状に注意が必要です。
二次性の抗菌薬反応性腸症に対しては、基礎疾患の治療を優先します。
抗菌薬反応性腸症に対して抗菌薬が効果を示す場合は、2週間以内に症状の改善が認められます。そのため、2週間以上投与しても症状が改善しない場合には、以下のように考えます。
- 他の抗菌薬に変更する
- 他の病気の可能性を考える
予後
基礎疾患が無ければ、原発性抗菌薬反応性腸症は治療によく反応します。この場合、比較的早期(2週間以内)に下痢の改善がみられます。
しかし、下痢が改善した場合でも、投薬の中止により下痢の再発を認めることが多いです。そのため、生涯にわたる投薬が必要となることもあります。
まとめ
犬の抗菌薬反応性腸症について解説しました。抗菌薬に反応して比較的短期間で症状の改善がみられる点では対処しやすい病気なのですが、多くの場合には生涯にわたる投薬が必要になる点では厄介な病気の一つです。
抗菌薬での治療に加えて、食事療法(低脂肪食や易消化性食)も必要になる場合がありますので、動物病院で獣医さんと相談されるとよいでしょう。