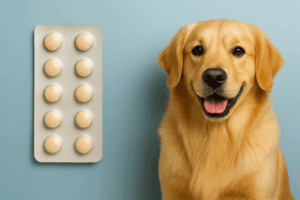「急にごはんを吐いてしまった」「食べたものをすぐ戻すけど、大丈夫?」――
犬の嘔吐は比較的よく見られる症状のひとつですが、その背景には軽い食べすぎから、命に関わる重篤な病気まで様々な原因が隠れていることがあります。
この記事では、犬の「急性嘔吐」について、獣医師の視点からその原因・症状・診断・治療・予後までをわかりやすく解説します。
この記事はこんな方におすすめです
- 犬が急に吐いてしまい、心配で様子を見ている飼い主さん
- 動物病院で「急性嘔吐」と診断されたが、詳しい説明を聞き逃してしまった方
- 獣医学生や動物看護師で、犬の嘔吐の臨床判断や対応について学びたい方
犬の急性嘔吐とは
嘔吐とは、胃の強い収縮により内容物が口から排出される現象を指し、時に小腸の内容物が混じることもあります。
嘔吐には「急性」と「慢性」があり、症状の経過日数によって分類されます。
一般に、6日以内に嘔吐が止まるものを「急性嘔吐」、7日以上続く場合を「慢性嘔吐」と呼びます。
似た症状に「嚥下障害」と「吐出」がありますが、それぞれ以下のように区別されます:
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| 嚥下障害 | 食べ物をうまく飲み込めない |
| 吐出 | 吐く仕草がなく、食道から内容物が戻ってくる(胃は関与しない) |
| 嘔吐 | 吐く前に腹部が収縮し、胆汁などが混じることが多い |
原因
急性嘔吐の最も一般的な原因は、不適切な食物の摂取(いわゆる「盗み食い」や「食べ過ぎ」)です。
その他にも、胃腸疾患や全身性疾患が関与していることもあります。
胃腸由来の原因
- 不適切な食物の摂取(腐敗食品、異物、過食など)
- 食物不耐症
- ウイルス性・細菌性胃炎
- 胃拡張捻転症候群
- 異物の誤飲
胃腸以外の全身性疾患
- 急性腎不全、慢性腎臓病
- 副腎皮質機能低下症(アジソン病)
- 糖尿病(特にケトアシドーシス時)
- 中毒(化学薬品・植物・食品など)
- 投薬の副作用(NSAIDs、抗がん剤など)
- 神経疾患(前庭疾患など)
- 急性膵炎、肝疾患、腹膜炎、子宮蓄膿症 など
急性嘔吐の症状
急性嘔吐は、単なる吐き戻しのように見える場合もあれば、ぐったりして元気がない、脱水、発熱、黄疸などの症状を伴うこともあります。
嘔吐と吐出の違いも重要です:
| 項目 | 嘔吐 | 吐出 |
|---|---|---|
| 発生部位 | 胃 | 食道 |
| 前兆 | 吐く仕草(腹部の収縮)あり | 吐く仕草なし |
| 内容物 | 胆汁が混じることが多い | 未消化の食べ物がそのまま出る |
⏱ 食後7〜10時間以上経っても未消化の食物を吐いた場合は、胃から腸への流出障害や運動性の低下が疑われます。
急性嘔吐の診断
まずは軽症例か重症例かを見極めることが重要です。
軽症例(嘔吐のみで元気・食欲は良好)
- 問診(食事内容、嘔吐の頻度、吐いた時間と内容など)
- 身体検査
- 必要に応じて経過観察しながら検査(血液検査・画像診断)を検討
例えば、混合ワクチンが未接種であればパルボウイルス性腸炎や犬ジステンパーが疑われ、また、非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs)やステロイド(グルココルチコイド)の投与歴がある場合には、薬剤による胃潰瘍の可能性も考慮します。
こうした情報は診断の大きな手がかりになるため、できるだけ詳しく獣医師に伝えることが大切です。
🔎 獣医師に伝えると診断がスムーズになるポイント
- 異物を食べた可能性があるか
- 食事の内容・変更の有無
- 嘔吐したものの特徴(色、量、におい、血液混入の有無など)
- 食後何時間で吐いたか
- 現在・過去の投薬歴(とくにNSAIDsやステロイド)
- ワクチンの接種歴
重症例(元気消失、脱水、発熱、黄疸などを伴う)
- 血液検査(肝腎機能、電解質、炎症マーカーなど)
- レントゲン・超音波検査(異物・腸閉塞・膵炎など)
- 尿検査・糞便検査
- 長引く場合には内視鏡検査も検討
急性嘔吐の治療
治療方針は、症状の重症度に応じて異なります。
まずは「軽症例」と「重症例」に分けて対応を考えます。
軽症例の場合
嘔吐以外の症状がみられず、犬が比較的元気な場合は「軽症例」とみなされます。
このような場合、治療の目的は「胃や腸を休ませること」にあります。
具体的には、以下のような対応が取られます:
- 12〜24時間の絶食・絶水
- 嘔吐が止まれば、少量の水から再開し、段階的に食事を戻す
- 消化しやすく低脂肪な食事を少量ずつ与え、数日かけて通常食に移行
無理に食事を与えず、消化管に負担をかけないようにすることが最も重要です。
重症例の場合
以下のような全身症状を伴う場合は、重症例として迅速な治療が必要です:
- 元気消失
- 脱水
- 発熱
- 黄疸
- 嘔吐の回数が多い/止まらない
この場合には以下のような対応を行います:
- 制吐剤の投与(吐き気止め)
- 点滴療法による水分・電解質の補正
- 原因疾患に応じた治療(例:中毒なら解毒処置、膵炎なら絶飲食+補液など)
- 状況に応じて入院管理を検討
予後
予後は原因によって大きく異なります。
- 不適切な食物摂取(盗み食い・食べ過ぎなど):数日以内に改善することが多い
- 全身性疾患や腸閉塞、胃拡張捻転症候群などが原因の場合:緊急手術や入院が必要になることもあり、慎重な経過観察と治療が必要です
⚠️ 繰り返す、または元気・食欲がない嘔吐は要注意です。早めの受診をおすすめします。
まとめ
犬の急性嘔吐は日常的に見られる症状ですが、軽症と重症の見極めが重要です。
単なる食べ過ぎで済むこともあれば、重大な疾患のサインであることも。
嘔吐が繰り返される、ぐったりしている、血が混じるなどの症状があれば、迷わず動物病院を受診してください。