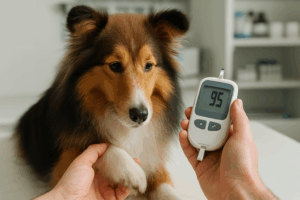動物病院で血液検査を受けた際、「BUN」や「クレアチニン」という項目の数値を見て戸惑った経験はありませんか?
これらは犬の腎臓の健康状態を把握するうえで非常に重要な指標であり、数値の変動にはさまざまな意味が隠されています。
BUN(血中尿素窒素)とクレアチニン(CRE)は、どちらも腎機能の評価に欠かせないマーカーですが、それぞれの値がどのような理由で上昇・低下するのか、またその違いは何かを知っておくことは、愛犬の健康管理においてとても重要です。
この記事では、犬の腎機能と密接に関わるBUNとクレアチニンについて、正常値や異常時に考えられる原因、さらには病気との関係まで、現役獣医師が科学的根拠に基づいてわかりやすく解説していきます。
ぜひ、血液検査の結果表をお手元に置いて、愛犬の健康状態を正しく理解するための参考にしてください。
・正常値は使用する検査機器や検査会社によって異なります。必ず検査結果用紙に記載された基準値を参照してください。
・検査結果が基準値を外れていても、必ずしも病気を意味するわけではありません。必ず担当獣医師の説明を受けましょう。
腎機能とBUN・クレアチニンの関係
腎臓は、血液中の老廃物や余分な水分をろ過し、尿として排泄する重要な臓器です。
この腎機能が低下すると、老廃物が体内に蓄積し、血液中の指標であるBUN(血中尿素窒素)とクレアチニン(CRE)の数値が上昇してきます。
これら2つは、腎臓の健康状態を評価する上で欠かせない指標であり、検査結果の読み解きにはそれぞれの特徴と違いを正しく理解することが大切です。
ここでは、まずBUNとクレアチニンについてそれぞれ詳しく解説し、その後に両者の相互関係についても触れていきます。
BUN(血中尿素窒素)とは
BUNは、タンパク質の代謝によって生じたアンモニアが肝臓で尿素に変換され、血液中に存在する尿素窒素の量を示しています。
通常、この尿素窒素は腎臓の糸球体でろ過され、尿として排出されます。
しかし、急性腎障害や慢性腎不全などで腎機能が低下すると、ろ過が追いつかなくなり、血液中のBUNが上昇します。
特に腎機能が正常の1/4以下に低下した場合、クレアチニンと同様にBUNも顕著に上昇するのが一般的です。
なお、BUNは腎機能以外の要因でも上昇することが知られています。たとえば、高タンパク食の摂取、消化管出血、発熱や火傷による組織損傷などが該当します。
こうした場合、腎障害がなくてもBUNだけが上昇するケースがあります。
| 検査会社 | 基準値 |
|---|---|
| 富士フィルムモノリス | 9.2~29.2 mg/dl |
| アイデックス(成犬) | 7.0〜27.0 mg/dl |
血中尿素窒素(BUN)高値の原因
BUN(血中尿素窒素)は、腎臓のろ過機能が低下した場合に上昇しますが、それだけではありません。
腎臓以外のさまざまな理由によっても上昇することがあるため、原因を大きく分けて理解しておくことが重要です。ここでは、「腎前性」「腎性」「腎後性」および「腎機能以外の原因」の4つのカテゴリーに分けて解説します。
腎前性(腎臓への血流低下によるもの)
腎臓自体に異常がなくても、血流不足により老廃物が十分に排泄されず、BUNが上昇するケースです。
腎性(腎そのものの障害によるもの)
腎臓自体がダメージを受けているため、ろ過機能が低下してBUNが増加する典型的なパターンです。
腎後性(尿の排出障害によるもの)
尿の出口が塞がれることで老廃物が体内にとどまり、BUNが上昇します。
| 腎後性の血中尿素窒素(BUN)高値の原因 |
| 閉塞性尿路疾患 尿路結石 尿路腫瘍 尿路周囲の腫瘍 |
腎機能以外の原因
これらは、腎臓が正常でもBUNが増える代表的な原因です。消化管出血や火傷などにより体内のタンパク質代謝が増えると、BUNの値が上がります。
| 腎臓の機能と無関係な血中尿素窒素(BUN)高値の原因 |
| 高蛋白の食事 消化管出血(胃や腸などからの出血) 火傷での筋肉の損傷 |
血中尿素窒素(BUN)低値の原因
逆に、BUNが基準値を下回る場合は、体内で尿素が十分に作られない、あるいは過剰に排泄されている状況が考えられます。
特に肝臓の機能が落ちると尿素の合成がうまくいかず、BUNが低下するケースはよく見られます。その他、食事や尿排泄の影響も考慮する必要があります。
| 血中尿素窒素(BUN)低値の原因 |
| 肝機能低下 肝硬変 低蛋白の食事 尿排泄量の増加 尿崩症 利尿剤使用時 |
クレアチニン(CRE)とは
クレアチニンは、筋肉のエネルギー源であるクレアチンリン酸が代謝されることで生じる老廃物です。
クレアチニンは常に一定量が血液中に産生され、腎臓の糸球体でろ過された後、再吸収されることなくそのまま尿中へ排泄されます。
そのため、クレアチニンの値は腎機能が低下した場合に非常に敏感に上昇し、腎障害の進行をダイレクトに反映する重要なマーカーとなります。
BUNと異なり、クレアチニンは高タンパク食や消化管出血などの腎機能以外の影響をほとんど受けません。
| 検査会社 | 基準値 |
|---|---|
| 富士フィルムモノリス | 0.4~1.4 mg/dl |
| アイデックス(成犬) | 0.5~1.8 mg/dl |
慢性腎臓病のステージ分類
この特性を活かし、慢性腎臓病(CKD)の重症度を示すステージ分類では、クレアチニン値が指標として用いられています。慢性腎臓病とは、両側あるいは片側の腎臓の機能的及び/あるいは構造的な異常が3ヶ月以上継続している状態です。
| ステージ | CRE(mg/dl) | 残存腎機能 | 症状 |
|---|---|---|---|
| ステージ1 | <1.4 | 33% | 非窒素血症、糸球体濾過量の減少、低比重尿 |
| ステージ2 | 1.4〜2.0 | 25% | 軽度の窒素血症 |
| ステージ3 | 2.1〜5.0 | 10% | 尿毒症症状 |
| ステージ4 | >5.0 | 5% | 生命維持に透析ないし腎移植が必要 |
クレアチニン(CRE)高値の原因
クレアチニンは、筋肉の代謝産物として生じ、腎臓の糸球体でろ過されることで尿中に排出されます。
腎臓のろ過機能が低下した場合、血液中のクレアチニン濃度が上昇しますが、BUNと同様に原因は「腎前性」「腎性」「腎後性」の3つに分類されます。
腎前性(腎臓への血流低下によるもの)
腎臓自体の障害ではなく、血流不足によりろ過量が減少し、一時的にクレアチニンが上昇するケースです。
腎性(腎そのものの障害によるもの)
腎臓そのものがダメージを受け、老廃物を十分に排泄できずクレアチニンが増加する、典型的な腎性の上昇原因です。慢性腎臓病では、このクレアチニン値に基づきステージ分類が行われます。
腎後性(尿の排出障害によるもの)
尿の通り道が塞がれることで、尿がうまく排出されず、体内に老廃物が蓄積してクレアチニンが上昇します。
| 腎後性のクレアチニン(CRE)高値の原因 |
| 閉塞性尿路疾患 尿素結石 尿路腫瘍 尿路周囲の腫瘍 |
クレアチニン(CRE)低値の原因
クレアチニンの値が低下する場合、基本的には腎機能障害というよりも筋肉量の減少や尿の過剰排泄が関与していることが多いです。クレアチニンは主に筋肉量に依存して産生されるため、筋肉が減少する疾患や高齢犬では低値になることがあります。また、尿量が極端に多い場合も、体内のクレアチニン濃度が薄まって低くなるケースがあります。
| クレアチニン(CRE)低値の原因 |
| 筋肉量の低下 筋萎縮 尿排泄量の増加 尿崩症 利尿剤使用時 |
BUNとクレアチニンの相互関係と診断のポイント
BUNとクレアチニンは、どちらも腎機能を評価する重要な指標ですが、異なる特徴を持っています。
- BUNは腎機能以外の要因(食事内容、消化管出血、脱水など)でも影響を受けやすいため、単独での判断は難しい場合があります。
- クレアチニンは比較的腎機能に特化した指標で、筋肉量を考慮しつつ腎障害の有無を評価するのに適しています。
したがって、これら2つの数値を組み合わせて評価することで、より正確に腎機能の状態を把握することができます。
たとえば、BUNとクレアチニンがともに上昇している場合は腎障害の可能性が高く、BUNのみが上昇している場合は脱水や消化管出血など腎外の原因も疑う必要があります。
まとめ
犬の腎機能を評価する上で、血中尿素窒素(BUN)とクレアチニン(CRE)の測定は非常に重要です。これらはどちらも腎臓の糸球体濾過機能の状態を反映しますが、異なる性質を持っているため、互いに補完することでより正確な評価が可能となります。
BUNは、食事の影響や消化管出血、脱水といった腎臓以外の要因でも数値が変動しやすい指標です。一方でクレアチニンは、腎機能により特化した指標であり、基本的には腎障害の有無を評価するのに優れています。ただし、筋肉量の影響を受けるため、高齢犬や筋肉量が少ない犬では注意が必要です。
BUNとクレアチニンの両方が高値を示している場合は、腎臓自体の障害(腎性)を強く疑いますが、BUNのみが高い場合には腎前性(脱水やショックなど)や腎後性(尿路閉塞など)といった他の原因も考慮する必要があります。
さらに近年では、より早期の腎障害を見つけるためにSDMA(対称性ジメチルアルギニン)などの新たな腎機能バイオマーカーも利用され始めています。
血液検査の結果が正常値から外れている場合でも、必ずしも即座に深刻な病気があるとは限りません。
そのため、腎機能の評価は血液検査だけで完結させるのではなく、尿検査(尿比重や尿蛋白)、画像診断(レントゲン、超音波)、その他の血液検査とあわせた総合的な判断が重要です。
腎臓は沈黙の臓器ともいわれ、症状が現れる頃にはかなり進行していることも多いため、日頃から定期的な健康チェックを行い、検査結果については必ずかかりつけの獣医師とよく相談するようにしましょう。