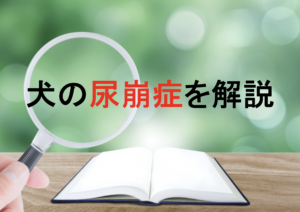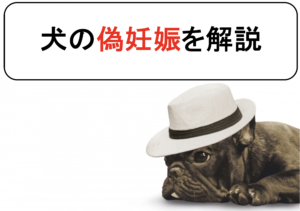愛犬が突然けいれんを起こし、意識を失うような発作が始まったら――
飼い主さんは驚きと不安でいっぱいになることでしょう。
特に1歳未満や6歳以上の犬に見られる症候性てんかんは、脳の病気が背景にあることが多く、早期の適切な診断と対応が重要です。
この記事では、犬の症候性てんかんについて、原因・症状・診断・治療・予後まで、現役獣医師がわかりやすく解説します。
愛犬のてんかん発作に不安を感じている方はもちろん、てんかんの知識を深めておきたい方も、ぜひ最後までご覧ください。
この記事はこんな方におすすめです
- 動物病院で「症候性てんかん」と診断された、または疑われている犬の飼い主さま
- 年齢や症状から特発性ではないてんかんを心配している飼い主さま
- 繰り返す発作の原因について、より深く理解したいと考えている方
- 犬のてんかんの診断や治療の流れを学びたい獣医学生や動物看護師の方
症候性てんかんとは
てんかんとは、大脳の神経細胞が異常に興奮することで引き起こされる、繰り返す発作が特徴の慢性的な脳の病気です。
このてんかんは、原因や背景によって大きく3つに分類されます。
特発性てんかん
脳に明らかな異常は認められないものの、遺伝的な素因などが関与して発作を繰り返すタイプです。多くは1〜5歳の若〜中年齢の犬に発症し、一般的には抗てんかん薬による長期管理が中心となります。
※詳しくは → [犬の特発性てんかんについて詳しくはこちら]
症候性てんかん
今回解説する症候性てんかんは、脳腫瘍や炎症、奇形などの脳に明らかな病変(器質的疾患)が原因となって発作が起こるタイプです。特に1歳未満の若齢犬や6歳以上のシニア犬で見られるケースが多く、基礎疾患に応じた治療が必要になります。
反応性てんかん(急性症候性発作)
分類上「てんかん」には含まれない場合もありますが、脳以外の病気や代謝異常が原因となり一時的に脳の神経活動が異常となって発作が起こるものです。
低血糖や肝疾患(門脈体循環シャントなど)、電解質異常、急性中毒(エチレングリコール、殺虫剤など)などが原因となります。これらはあくまで全身性の異常が脳へ影響しているだけで、脳自体に慢性的な病変があるわけではないのが特徴です。原因疾患の治療・改善により発作も治まります。
このように、てんかん発作といっても背景や原因はさまざまです。
この記事では、特に脳の病気が原因で発生する「症候性てんかん」について詳しく解説していきます。
原因
原因となる疾患には、脳の奇形、外傷、脳腫瘍、脳血管障害、脳炎など多岐にわたるものがあり、これらの病気が脳の正常な神経活動を乱すことで発作を引き起こします。
なお、犬猫全体のてんかん発作のうち、症候性てんかんが占める割合はおよそ50%とされており、非常に重要なタイプのひとつです。
| 症候性てんかんの原因 |
| 脳の奇形 水頭症、大脳皮質形成障害、くも膜嚢胞など 脳の外傷 交通事故など 脳腫瘍 髄膜腫、神経膠腫(グリオーマ)など 脳炎 ・感染性(例、犬ジステンパーウイルスなど)、 ・非感染性( 例:壊死性髄膜脳炎(パグ脳炎)、壊死性白質脳炎、肉芽腫性脳脊髄炎など) 脳血管障害 脳出血、脳梗塞など 変性疾患(先天性代謝疾患) ライソゾーム病、ラフォラ病、セロイドリポフスチン病、ガングリオシドーシスなど |
症候性てんかんの症状
症候性てんかんでは、発作が起こる部位は主に大脳皮質です。
この大脳皮質は、運動や感覚など多くの重要な神経活動を司る場所で、ここに異常が起きるとてんかん発作が引き起こされやすくなります。
発作が始まる場所(てんかんの焦点)は、
- 病巣そのものが焦点となるケース(例:表面に位置する脳腫瘍など)
- 病巣自体ではなく、隣接する正常な神経細胞が病巣の影響を受けて異常興奮し、焦点となるケース(例:腫瘍や炎症による圧迫や波及によるもの)
の2つのパターンが考えられます。
代表的な症状の例
- 壊死性脳脊髄炎(パグ脳炎)や脳表面にできた腫瘍などは、病変が大脳皮質に近いため、初期症状としててんかん発作が現れやすいことが知られています。
- 一方で、小脳や脳幹に限局した病変のみでは、基本的にてんかん発作は生じにくいとされています。
ただし、病気が進行し、炎症や浮腫、脳ヘルニアなどの影響が大脳まで波及した場合には、発作が引き起こされる可能性もあります。
このように、てんかん発作の有無や現れ方は、病変の部位や原因疾患の進行状況によって大きく異なるのが特徴です。
症候性てんかんの診断
症候性てんかんを診断するためには、まず本当に「てんかん発作」であるかを正確に判断する必要があります。
そのうえで、以下の流れで診断を進めていきます。
- てんかん発作の確定
- 他の病気による一時的なけいれん(失神や中毒など)ではないかを見極めます。
- 反応性てんかん(急性症候性発作)の除外
- 低血糖や電解質異常、中毒など、脳以外の全身的な問題が原因ではないかを確認します。
- 特発性てんかんの可能性を検討
- 年齢(通常は1〜5歳に多い)や家族歴、神経学的異常の有無などから、特発性てんかんである可能性を評価します。
この結果、特発性てんかんの可能性が低い場合、症候性てんかんの可能性が高まります。
この場合は、より詳細な検査を行い、原因疾患を特定することが重要です。
具体的には、
- 脳MRI検査(腫瘍・奇形・炎症などの可視化)
- 脳脊髄液検査(炎症や感染の有無を調べる)
これらの精密検査を実施します。
なお、神経学的検査で異常が認められれば、より症候性てんかんの可能性は高まります。
しかし、症候性てんかんの犬の約23%では、神経学的検査上に異常が見られないとの報告もあり、正常所見だからといって完全には除外できない点も重要です。
症候性てんかんの治療
症候性てんかんの治療は、発作のコントロールと原因疾患の治療の両立が基本です。
まず、発作そのものについては、特発性てんかんと同様に抗てんかん薬による発作抑制を行います。
これにより、生活の質(QOL)を維持し、重積発作などのリスクを軽減します。
一方、原因疾患の治療も同時に進めます。
例えば、
- 脳腫瘍 → 外科手術・放射線治療など
- 免疫介在性脳炎 → ステロイド(プレドニゾロン)や免疫抑制剤の投与
- 水頭症 → 脳室腹腔シャント術など
このように疾患ごとに最適な治療が選択されます。
また、根治が難しいケースでも、
- 脳浮腫や脳圧亢進の管理(降圧剤、ステロイドなど)
- 疼痛の緩和や生活のサポート
などの対症療法を積極的に行うことで、QOLの維持を目指します。
予後
予後は、やはり原因疾患の種類と重症度に大きく左右されます。
- 進行性の脳疾患(悪性腫瘍や重度の炎症など)が原因の場合は、発作の増悪や重積発作のリスクも高く、予後は厳しいケースが多くなります。
- 一方、手術や内科的治療によって原因疾患が安定化した場合や、非進行性の原因であれば、抗てんかん薬を用いて良好に発作をコントロールし、長期間の維持が可能なケースもあります。
このように、症候性てんかんは原因によって経過が大きく異なるため、診断後は担当獣医師としっかり相談し、個々に応じた治療方針を決めていくことが大切です。
まとめ
犬の症候性てんかんは、脳腫瘍や脳炎、奇形など、脳内の疾患が原因で発作が引き起こされるタイプのてんかんです。特に1歳未満や6歳以上の犬で発症する場合には、このタイプが疑われることが多くなります。症状の背景には、脳の表面に病変があるケースから、深部の病変が進行して発作を誘発するケースまでさまざまなパターンがあります。
診断には、神経学的検査のほか、MRIや脳脊髄液検査といった精密検査が欠かせません。発作を繰り返しているだけでは特発性てんかんとの区別は難しいため、原因となる病気を正確に見極めることが治療の出発点となります。
治療は、抗てんかん薬による発作の抑制に加え、原因疾患に応じた対策が必要です。外科手術や放射線、免疫抑制療法などが選択されることもあり、根治が難しい場合には対症療法によって生活の質を維持することが重要になります。
予後は原因疾患の内容によって大きく異なりますが、治療により安定した状態を保てるケースも少なくありません。愛犬の発作が症候性てんかんによる可能性がある場合は、早期の検査と適切な治療方針の立案が、今後の生活の安定に繋がります。