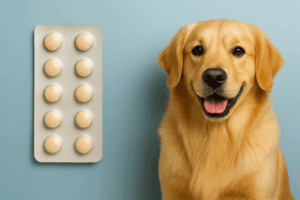愛犬の下痢が何日も、あるいは何週間も続く――
そんな状況に直面すると、飼い主さんは不安や心配でいっぱいになることでしょう。
犬の慢性下痢は、動物病院を訪れる理由として非常に多くみられる症状のひとつです。
時に原因の特定や治療に時間がかかり、長期的な管理が必要になることもあります。
この記事では、犬の慢性下痢について、原因・症状・診断・治療・予後まで、現役獣医師が丁寧に解説します。
愛犬の下痢がなかなか治らず不安な方、また慢性下痢について正しい知識を身につけたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事はこんな方におすすめです
- 動物病院で「慢性下痢」と診断された、または疑われている犬の飼い主さま
- 下痢が長期間続き、心配している飼い主さま
- 犬の慢性下痢について学びたい獣医学生や動物看護師の方
慢性下痢とは
下痢とは、消化機能の異常により、普段より水分の多い柔らかい便が出る状態を指します。
便の状態によって、以下のように分類されます。
- 軟便:ギリギリ掴める程度の柔らかさ
- 泥状便:泥のように柔らかく掴めない状態
- 水様便:水のようにさらさらとした便
犬の下痢は、多くの場合は数日以内に治まる「急性下痢」として現れますが、3週間以上続く場合は「慢性下痢」と呼ばれます。
慢性下痢は、急性下痢と異なり原因の特定が難しく、治療にも時間がかかるケースが多いのが特徴です。
典型的には、「急性下痢は激しい症状でも比較的早く治る」のに対し、「慢性下痢は症状は緩やかでもなかなか改善しない」ことが多いと言えます。
長引く下痢は、犬の体力や栄養状態に影響を与えるため、原因をしっかり突き止め、適切な対応をすることが重要です。
原因
慢性下痢は、さまざまな疾患や要因が複雑に関与して起こるため、原因を特定するのが難しいこともあります。
大きくは、小腸や大腸における異常、あるいは全身性の疾患などに分けて考えられます。
慢性下痢の主な原因は、次の3つに分類されます。
- 小腸と大腸のどちらにも影響する病気(例:炎症性腸疾患[IBD]、食物アレルギーなど)
- 小腸性下痢を引き起こす病気(例:腸リンパ管拡張症、膵外分泌不全、副腎皮質機能低下症など)
- 大腸性下痢を引き起こす病気(例:細菌や寄生虫感染、繊維反応性下痢、腫瘍など)
小腸性下痢では、便の量が増えて体重減少が見られることが特徴です。
一方、大腸性下痢では、便の回数が増え、少量ずつ排便するのが特徴で、体重減少はあまりみられません。
| 慢性下痢の原因 |
| 小腸性下痢も大腸性下痢も起こす病気 炎症性腸疾患(IBD) 食物(食物不耐性、食物アレルギー) 小腸性下痢を起こす病気 腸リンパ管拡張症 抗菌薬反応性腸症 膵外分泌不全 副腎皮質機能低下症(アジソン病) 肝不全 腫瘍(リンパ腫など) 大腸性下痢を起こす病気 細菌(クロストリジウム属など) 寄生虫(鞭虫、ジアルジア、コクシジウムなど) 繊維反応性下痢 腫瘍(腺癌、良性ポリープ、リンパ腫など |
慢性下痢の症状
慢性下痢は、発症から3週間以上続くのが特徴です。
急性下痢と比べて症状は緩やかですが、長期間にわたって愛犬の体に負担を与えます。
症状は、病気が小腸性か大腸性かによって異なります。
小腸性下痢の場合
- 便の回数は通常と変わらないか、やや増加する程度
- 1回あたりの便の量が多い
- 消化吸収が悪いため、体重減少がみられる
大腸性下痢の場合
- 便の回数が多く、少量ずつ何度も排便する(しぶり)
- 体重減少はあまりみられない
- 血便(鮮血便)が出ることがある
- 黒色タール状の便(メレナ)が見られた場合は、より重篤な病気を疑う必要がある
その他の症状
- 腹痛が強い場合、「祈りの姿勢」や「背湾姿勢」が見られる
- 腸リンパ管拡張症では、浮腫や腹水がみられることがある
- 腹痛や腫瘤(できもの)が触れる場合がある(リンパ腫などの腫瘍時)
慢性下痢は、こうした便の状態や付随する症状から小腸性か大腸性かを推測する手がかりになりますが、必ずしも単純に区別できるわけではないため、正確な診断が欠かせません。
慢性下痢の診断
慢性下痢は、急性下痢と異なり必ず検査が必要になります。
単なる消化不良や一過性のものではなく、何らかの基礎疾患が隠れている可能性が高いためです。
まず、診察では次のような基本的な検査が行われます。
初期検査(基本検査)
- 糞便検査(寄生虫や細菌の有無を確認)
- 血液検査(全身状態や感染・炎症の有無を評価)
- レントゲン検査・超音波検査(腫瘍や腸管異常、腹水などの確認)
- 尿検査(腎疾患や全身状態の把握)
これらによって、まずは重篤な疾患や急を要する病態を除外していきます。
詳細検査(精密検査)
さらに必要に応じて、以下のようなより詳しい検査が実施されることがあります。
- 尿蛋白/クレアチニン比(UPC)
- 血清総胆汁酸試験(TBA)
- ACTH刺激試験(副腎機能を調べる検査)
- トリプシン様免疫反応活性試験(TLI)(膵外分泌不全の評価)
- 血清コバラミン(ビタミンB12)・葉酸濃度(小腸機能の確認)
- 内視鏡検査・生検(腸の粘膜を直接観察・組織採取)
- 試験的開腹手術(内視鏡では診断が難しい場合に実施)
慢性下痢の場合、原因を突き止めることが治療方針を決める上でも非常に重要です。そのため、検査は段階的かつ包括的に行うのが一般的です。
慢性下痢の治療
慢性下痢の治療は、原因によって異なります。
軽度のものから重度の疾患まで幅広く、緊急的な対処と長期的な管理の両面からアプローチする必要があります。
緊急的な治療(支持療法)
まずは症状を緩和し、犬の体力を保つために次のような食事療法が行われます。
- 容易に消化できる低脂肪食を少量ずつ与える(1日3〜6回の頻回給餌)
- 低脂肪カッテージチーズ、豆腐、米、ジャガイモなどの利用
- 大腸性下痢が疑われる場合は高繊維食が有効
これらによって腸管への刺激を抑え、症状の悪化を防ぎます。
また、必要に応じて以下の薬物療法を併用することがあります。
- 駆虫薬(寄生虫感染が否定できない場合は経験的に投与)
- 抗菌薬(細菌感染や抗菌薬反応性腸症が疑われる場合)
- 整腸剤(腸内環境を整えるため:ビオイムバスターなど)
長期的な治療(原因療法)
慢性下痢は基礎疾患の治療が最も重要です。
検査で原因が判明した場合、以下のような治療が行われます。
- 炎症性腸疾患(IBD)や食物アレルギー
→ 食事療法(除去食試験や加水分解食など)、免疫抑制剤 - 膵外分泌不全
→ 膵酵素製剤(パンクレアチンなど)の補充 - 腫瘍(リンパ腫、腺癌など)
→ 化学療法や外科手術 - 腸リンパ管拡張症
→ 低脂肪食、利尿剤、免疫抑制剤 - 副腎皮質機能低下症(アジソン病)
→ 副腎ホルモンの補充療法
このように、慢性下痢の治療は一過性のものではなく、生涯にわたる管理が必要になるケースも多いのが特徴です。
予後
慢性下痢の予後は、原因となる基礎疾患によって大きく異なります。
腫瘍(リンパ腫・腺癌)、腸リンパ管拡張症、抗菌薬反応性腸症、炎症性腸疾患(IBD)などは、長期的な治療が必要となるケースが多く、症状の再燃を繰り返すこともあります。
一方で、食物不耐性・アレルギー、細菌・寄生虫感染、膵外分泌不全、副腎皮質機能低下症(アジソン病)などは、適切な治療により比較的良好な経過が期待できます。
慢性下痢は、生涯にわたる管理が必要となる場合もあるため、獣医師と十分に相談しながら無理のない治療を継続することが大切です。
まとめ
犬の慢性下痢は、短期間で治る急性下痢とは異なり、治療が長期にわたる場合が少なくありません。
原因によっては完治が難しいケースもあり、症状が良くなったり悪化したりを繰り返すこともあります。
しかし、適切な診断と治療を行えば、症状のコントロールが可能な場合も多く、食事管理や内服薬によって安定した生活を送ることができます。
愛犬の慢性下痢で困ったときは、無理せず獣医師に相談し、愛犬と飼い主の生活スタイルに合った治療法を一緒に考えていくことが大切です。